休業損害とは?職業別の計算方法や請求の注意点も解説
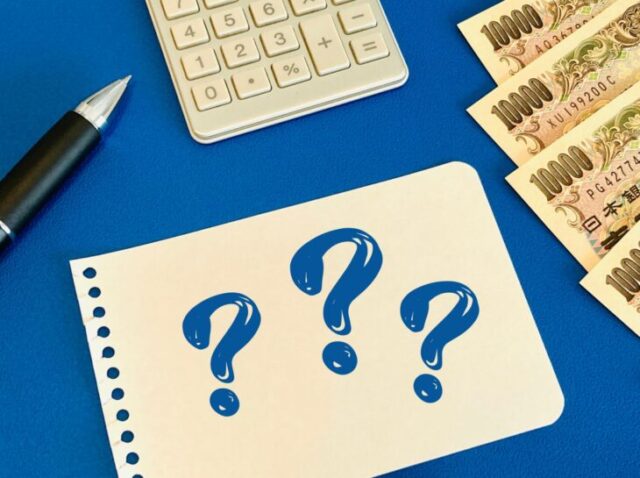
「休業損害とはどのようなものなのか」
「どのように計算すればいいの?」
「適正な金額を計算するためのポイントについて知りたい」
交通事故に遭い、怪我の治療などで仕事を休まなければならなくなった方の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
事故による怪我の治療のために入院や通院をする場合には、仕事を休まなければならないケースもあり、そのような場合には収入が減少してしまいます。
もっとも、そのような理由による収入の減少については、加害者側から補償を受けることが可能です。
これは、交通事故の損害項目の1つで、休業損害と呼ばれています。
本記事では、休業損害の概要や具体的な計算方法などについて解説します。
また、適正な金額の休業損害を受け取るためのポイントについても解説しています。
休業損害の算定は複雑な点もあるため、不安な点や悩みがある場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
1.休業損害の概要

休業損害は、交通事故の損害項目の1つです。
以下では、休業損害の概念や、労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)による休業補償給付との違いなどについて解説します。
なお、休業損害の詳細や請求を行うための条件については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
(1)休業損害とは
休業損害とは、交通事故による怪我の治療のために被害者が休業又は十分な稼働ができなかったことから、症状固定時までに生じた収入の減少に対する賠償のことをいいます。
交通事故の被害者は、事故と因果関係のある休業損害を加害者に請求し、受け取ることができます。
休業損害は、収入の減少を補填するものであるため、原則として事故前に労働によって収入を得ていたことが前提となります。
そのため、就労していない人や家賃収入などの不労所得を得ていた人等は、事故によって減収が生じたとはいえないため、休業損害を受け取ることができません。
もっとも、主婦(夫)などの家事労働に従事している人は、現実に収入を得ていませんが、休業損害を受け取ることが可能な場合があります。
なお、加害者側の保険会社に休業損害を請求する方法については、以下の記事もご参照ください。
(2)休業補償給付との違い
休業補償給付は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づき、労災保険から受給することができる保険給付です。
休業補償給付は、療養のために労働できず、賃金を受けない日の4日目から支給されます(業務災害の場合、最初の3日間は、労働基準法により使用者に支払い義務が課されています。)。
休業補償給付は、仕事を休まざるを得なくなったことに対する補償という点では、休業損害と類似しています。
もっとも、労災保険の休業補償給付は、原則として基礎日額の60%に相当する金額の支給にとどまります。
そのため、過失割合が40%未満の場合には、休業損害の賠償を受けた方が経済的にメリットがあると言えます。
なお、休業損害と休業補償給付は、どちらも収入の減少を補償するためのものであることから、二重に受け取ることはできないことに注意が必要です。
休業損害と休業補償給付の細かな違いや請求方法、注意点などについては、以下の記事が参考になります。
(3)休業損害を受け取れる時期
損害賠償請求としての休業損害は、示談金の一部として示談交渉の時点で請求を行い、受け取ることが原則です。
もっとも、交通事故による休業の必要性及び相当性を保険会社が認めた場合などには、示談が成立する前に支払いを受けることが可能なケースもあります。
休業損害を受け取る時期や手続の流れについては以下の記事も合わせてご参照ください。
また、休業損害を示談成立前に受け取る方法や支払いを拒否された場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
2.休業損害の算定基準

休業損害は、原則として、1日あたりの基礎収入×休業日数で算出されます。
そして、休業損害の基礎収入の定め方の基準は大きく分けて3つあり、どの基準を採用するかによって金額が変動します。
具体的には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所(弁護士)基準
休業損害の算定基準と計算方法については、以下の記事もご参照ください。
(1)自賠責基準
自賠責基準では、原則1日あたりの基礎収入は6,100円と決められています。
もっとも、日額が6,100円を超えることが立証できれば、その金額で算定されます(上限あり)。
休業日数については、交通事故を原因として実際に休業した日数又は使用した有給休暇の日数(時間数)が算定の基礎となります。
家事従事者の場合には、通院日数を参考に定められることがほとんどです。
自賠責保険はこのように、算定方法を明確化しているため、分かりやすいのが特徴です。
もっとも、自賠責保険は、休業損害のほか、治療費や慰謝料等全ての損害額を合計して120万円までしか支払われないため、注意が必要です。
(2)任意保険基準
任意保険会社が独自に定める算定基準です。
保険会社が示談交渉で提示する休業損害の額は、この基準によって算出されています。
具体的な算定基準は非公開となっていますが、自賠責基準と同額かやや上回る程度の水準であることが多いです。
日額を算定する際には、事故前3か月の収入を単純に90日で割っていることがほとんどであり、不当に日額が低くなってしまっていることがあります。
そのため、保険会社が提示する金額のまま示談に応じてしまうと、適正な金額を受け取ることができない可能性があります。
少しでも金額に疑問や不安がある場合には、安易に提案に応じず、まずは弁護士に相談して確認を依頼するのがおすすめです。
(3)裁判所(弁護士)基準
これは、過去の裁判例に基づいて導出された算定基準であり、3つの中で最も適正な算定方法となります。
被害者の職業ごとに基礎収入の算定方法が異なるところに特徴があります。
弁護士に依頼することで、裁判所(弁護士)基準に基づいた適正な休業損害を請求し、受け取ることが可能になります。
具体的な計算方法については、次項で詳しく解説します。
3.職業別|休業損害の計算

裁判所(弁護士)基準を用いて休業損害の算出を行う場合、基礎収入の考え方が職業によって異なります。
主な職業別の基礎収入の考え方は、以下のとおりです。
- 給与所得者(サラリーマン、パート・アルバイト)
- 事業所得者
- 家事従事者(主婦、主夫)
- 会社役員
- 無職・失業者
それぞれの計算方法についてご説明します。
(1)給与所得者(サラリーマン、パート・アルバイト)
サラリーマンなどの給与所得者の休業損害の算定方法は、以下のとおりです。
- 事故前3か月の支給金額の合計÷90日(または実稼働日数)×休業日数
事故前3か月の支給金額には、基本給等の本給だけでなく、残業代や各種手当等の付加給も含めて計算します。
また、税金や社会保険が差し引かれる前の金額に基づいて計算を行う点もポイントです。
割る日数は、休業日数に休日が含まれている(一定期間の連続した休業)なら90日、含まれていない(飛び石の休業)なら実稼働日数とするのが適切です。
事故前の3か月間の支給金額や休業日数については、勤務先が発行する「休業損害証明書」に基づいて証明を行う必要があります。
休業損害の請求を行う際には、あらかじめ保険会社から書式を入手して勤務先に提出し、同証明書の発行を受けましょう。
なお、賞与が減額された場合についても、休業損害として計上できます。
この場合は「賞与減額証明書」の発行を受けましょう。
(2)事業所得者
自営業者や個人事業主、フリーランスなどの事業所得者が、事故前の所得をもとに休業損害を算出する場合は、以下の算定式に基づいて計算を行います。
- (事故前年の所得金額+固定経費)×寄与率÷365日×休業日数
事故前年の所得額は、確定申告書の記載内容に基づいて証明を行うことが一般的です。
また、休業中に支出しなければならなかった賃料やリース料等の固定経費についても、基礎収入に含めて計算することができます。
なお、寄与率とは事業者本人の稼働に基づく収益部分の度合いを指すものです。
たとえば、事業者本人が、完全に1人で収益を得た場合には、寄与率は100%となります。
計算方法の詳細やポイントについては、以下の記事も参考になります。
(3)家事従事者(主婦、主夫)
家事従事者とは、性別・年齢を問わず、自分以外の家族のために実際に家事労働に従事する者をいいます。
家事従事者は、家事労働による収入を得ていませんが、交通事故による怪我によって家事労働に従事できなくなった場合には、休業損害を受け取ることができます。
具体的には、以下のように算定します。
- 女性労働者の全学歴計・全年齢平均年収額÷365日×休業率×休業日数
家事従事者の基礎収入は、厚生労働省が毎年公表している「賃金センサス」と呼ばれる統計資料に基づいて算出します。
当該家事従事者が男性であっても、女性労働者の平均年収額に基づいて算定が行われる点に注意が必要です。
また、休業が長期にわたる場合は、全く労働できなかった場合を休業率100%とし、受傷内容や治療経過等によって一定割合(休業率)のみを賠償対象とする計算をすることがあります。
なお、パート労働などで収入を得ている兼業主婦(主夫)の場合には、上記の算定式に基づく休業損害と勤務先での給与等に基づいた休業損害を算出し、金額が高い方を受け取ることが可能です。
主婦(主夫)の休業損害を算定する際のポイントや注意点などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
(4)会社役員
役員報酬は、一般的に当該会社の利益配当の意味を持ちます。
そのため、休業損害が認められるかについては、消極的に考えられています。
もっとも、会社の規模が小さかったり、取締役とは名目だけで実際には従業員と同様の業務を行っていたりする場合、労務の対価と考えられる部分もあり得ます。
そこで、会社役員の場合には、以下の算定式に基づいて休業損害を計算します。
- 労務対価部分の報酬(役員報酬全額-利益配当部分の報酬)÷365日×休業日数
どの部分が労務対価部分の報酬に当たるかについては、実際には年齢や地位、会社の規模などの複雑な要素を考慮に入れた上で総合的に判断されることが多いです。
ご自身で計算を行うことには困難なことが多いですので、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
会社役員の休業損害の計算方法や注意点などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(5)無職・失業者
交通事故に遭った時点で無職であったり失業していたりした場合には、事故による減収がないため、原則として休業損害は認められません。
しかし、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、例外的に休業損害を請求し、受け取ることが可能なケースもあります。
たとえば、事故に遭った時点ですでに内定を得ていた場合や求職活動の状況などから事故に遭わなければ就労していた可能性が高いといえる場合には、休業損害の請求が認められるケースがあります。
もっとも、就労の可能性や基礎収入などは、具体的に立証する必要があります。
そのため、ご自身が休業損害を請求できる可能性があるのかどうかについては、弁護士にご相談になることをおすすめします。
交通事故の時点で無職である人が休業損害を請求するための条件や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
4.適正な休業損害を受け取るためのポイント
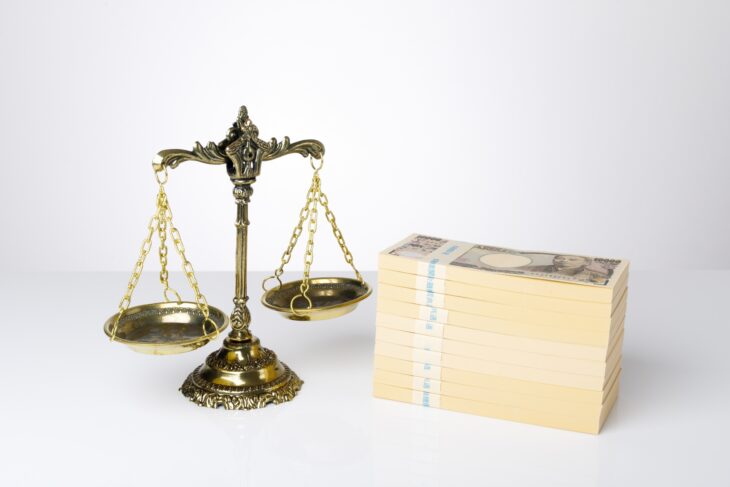
休業損害は、計算が複雑になることが多くあります。
正しく計算ができなければ、本来受け取ることができたはずの相場よりも低い金額しか受け取れない可能性があります。
適正な休業損害を計算するため、以下の点を押さえておきましょう。
- 弁護士に相談する
- 実際の収入をもとに計算する
- 休業日数を正しく求める
- 休業損害証明書の内容を確認する
- 保険会社が提示する金額を鵜呑みにしない
順にご説明します。
なお、適正な金額を計算するためのコツについては以下の記事でも解説しています。
(1)弁護士に相談する
休業損害の計算は複雑であり、正しい知識や経験がなければ適正な金額を算定することは困難です。
そのため、休業損害の計算に不安や疑問がある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、休業損害を適正に計算するためのサポートやアドバイスを受けることができるほか、必要書類の準備についてもサポートを受けられます。
また、弁護士にご相談になると、休業損害だけでなく、損害賠償金の項目全般について説明を受けることができます。
適正な金額の算定と請求を行うためにも、まずは弁護士に相談することが最も大切です。
(2)実際の収入をもとに計算する
上でみたとおり、自賠責基準では、原則として、1日あたりの基礎収入を6,100円として算定することになります。
それ以上の収入を得ている場合には、その収入金額を立証し、請求を行うことが必要になります。
ただし、たとえ高額な収入を立証したとしても、自賠責基準では、1日あたりの基礎収入は最大で19,000円までしか認められないことに注意が必要です。
また、120万円の上限額の定めもあります。
そのため、これらの制限を受けずに適切な休業損害の賠償を受けるためには、裁判所(弁護士)基準を用いて算定することが必要になります。
もっとも、被害者ご自身が保険会社と交渉を行っても、保険会社が裁判所(弁護士)基準に基づく休業損害を認めることはほとんどありません。
実際の収入を反映した適正な金額を受け取るためには、弁護士に交渉を依頼しましょう。
(3)休業日数を正しく求める
休業日数は、交通事故による怪我について医療機関を受診した初日(初診日)から完治または症状固定までの期間が対象となります。
休業日数には、入院・通院に要した日数だけでなく、自宅療養によって仕事を休んだ日数も含められる場合があります。
もっとも、休業した全ての日に対して休業損害が認められるわけではなく、休業日数として具体的にどのくらいの日数が認められるかは、怪我の程度や治療経過、被害者の職種などから総合的に判断されるものです。
また、治療のために有給休暇を消化した場合にも、その日数又は時間数を休業日数に含めることができます。
休業日数と有給休暇の日数の関係については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
(4)休業損害証明書の内容を確認する
給与所得者が休業損害を請求するためには、勤務先が作成する「休業損害証明書」という書類が必要になります。
「休業損害証明書」には、休業日数や休業期間中の給与の支払いの有無、事故前3か月に支給された給与額などを記載してもらう必要があります。
給与所得者の休業損害の基礎収入については、「休業損害証明書」の記載内容に基づいて主張・立証を行います。
そのため、記載内容に誤りがあれば、実際に受け取ることができる休業損害の額が減少してしまうため、注意が必要です。
休業損害証明書の概要や記載項目、作成の際の注意点などについては、以下の記事もご覧ください。
(5)保険会社が提示する金額を鵜呑みにしない
保険会社が提示する休業損害の金額は、任意保険基準に基づいて算出されます。
前述したように、任意保険基準は自賠責基準とほぼ同等の水準であり、保険会社の提示を鵜呑みにしてしまうと、受け取れる休業損害が相場よりも低額になってしまう可能性があります。
そのため、保険会社から休業損害の提示があった場合には、すぐに応じず、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、被害者の属性や状況に応じて、増額の余地がないかについて、チェックとアドバイスを受けることができます。
まとめ
本記事では、休業損害の意義や具体的な計算方法などについて解説しました。
交通事故によって怪我を負い、治療のために入院や通院をした場合には、それによる収入の減少を加害者側に請求し、休業損害として受け取ることが可能です。
もっとも、適正な金額を受け取るためには、いくつかの注意点とポイントがあります。
そのため、ご自身が具体的にどのくらいの休業損害を受け取れる可能性があるのかなどについて知りたい方は、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまで多くの交通事故の法的手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、休業損害の計算や請求についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事































