交通事故の被害者が利用できる保険とは?利用の際の注意点についても解説

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故に遭ってしまった場合に利用できる保険にはどのようなものがある?」
「受け取ることができる保険金の種類について知りたい」
「保険を利用する際に押さえておくべきポイントはある?」
交通事故に遭い、車が壊れたり怪我の治療をしている方の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
交通事故の被害者が利用できる保険は、加害者側の任意保険が代表的ですが、状況によっては被害者ご自身の保険を利用することも可能です。
保険の種類や契約時の条件などによって受け取ることができる保険金の金額や補償を受けられる項目には違いがあるため、保険内容を確認しておくことが重要です。
本記事では、交通事故の被害者が利用することができる保険や受け取ることができる保険金の種類などについて解説します。
また、保険を利用する際の注意点についても合わせて解説しています。
1.交通事故の被害者が利用できる保険

交通事故の被害者は、加害者側の保険あるいは被害者自身の保険を利用することができます。
加害者が任意保険に加入している場合には、加害者の任意保険会社が賠償などに関する対応を行うのが原則です。
また、怪我の治療費に関しては、保険会社が任意に支払いを行う一括支払対応を受けられることが多いです。
もっとも、加害者が自賠責保険にしか加入していない場合や加害者側の保険会社が支払いを拒否した場合などには、被害者自身の保険を利用することを検討する必要があります。
被害者が利用できるそれぞれの保険の概要や補償内容については、次項で詳しく解説していきます。
なお、交通事故の被害者が受け取ることができる一般的な保険金の項目については、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
2.被害者が利用できる加害者側の保険
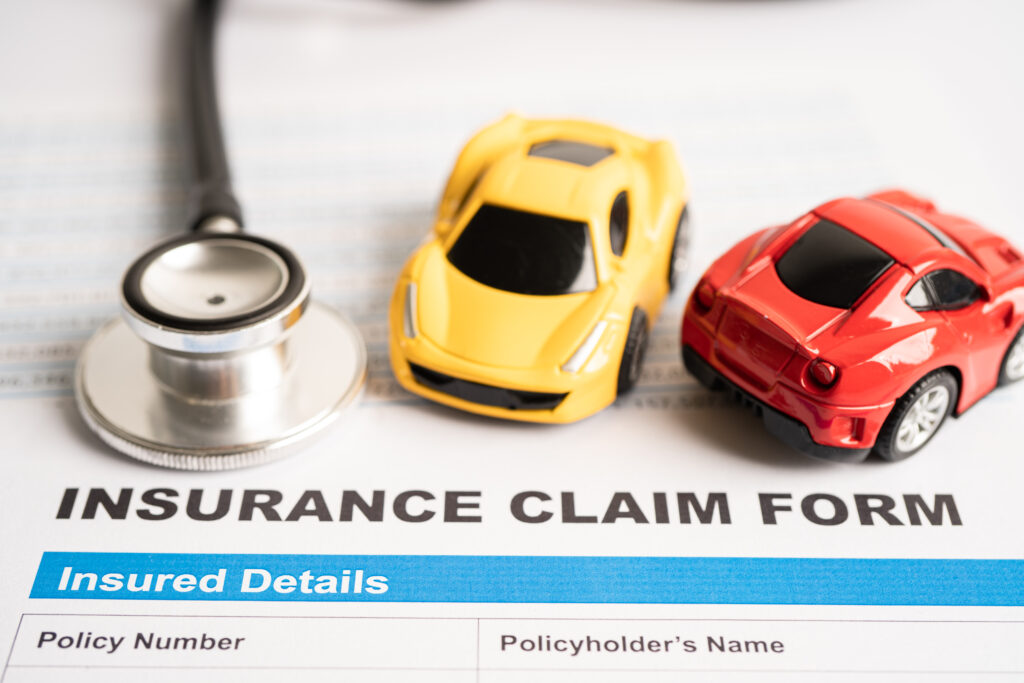
被害者が利用できる加害者側の保険には、以下のものがあります。
- 任意保険
- 自賠責保険
加害者が任意保険に加入している場合には、基本的に加害者側の任意保険から賠償金を受け取ることになります。
もっとも、加害者が任意保険に加入していない場合や交渉が進まない場合には、加害者側の自賠責保険から補償を受けることも検討する必要があります。
それぞれの保険の概要や保険金の項目について解説します。
(1)任意保険
加害者が任意で加入している保険を指します。
保険によって補償内容が異なるものの、主に以下のような保険が利用できます。
- 対人賠償保険
- 対物賠償保険
繰り返しになりますが、加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険から賠償金を受け取ることができます。
そのため、被害者が利用する加害者側の保険は、ほとんどの場合が任意保険のみとなります。
#1:対人賠償保険
対人賠償保険は、交通事故によって、相手が怪我を負ったり、死亡したりした場合の人的損害の賠償を補償する保険です。
被害者は、対人賠償保険に対し、怪我の治療費や傷害(入通院)慰謝料、休業損害などを請求することができます。
怪我の治療を継続した後に後遺症が残り、それが後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することもできます。
このように、交通事故における人的損害については、対人賠償保険がカバーしていると言えます。
#2:対物賠償保険
対物賠償保険は、交通事故によって生じた物的損害の賠償について、保険会社が代わりに支払うものです。
被害者は、加害者が加入している対物賠償保険から車両の修理費や代車費用などを受け取ることができます。
対物賠償保険の補償内容や注意点などについては、以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。
(2)自賠責保険
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限度の補償を行うことを目的とした保険で、車の所有者全員に加入が義務付けられているものです。
そのため、加害者が任意保険に加入していない場合や交渉が進まない場合、被害者に高い過失割合が認められる場合には、例外的に自賠責保険を利用することを検討しましょう。
もっとも、自賠責保険から受け取ることができるのは人的損害についての補償のみであり、物的損害については補償を受けることができない点に注意が必要です。
また、最低限度の損害の補償を目的としているため、受け取ることができる保険金額に上限があることや重過失減額が生じる場合もある点にも注意しておきましょう。
自賠責保険における過失割合の考え方については、以下の記事をご参照ください。
また、自賠責保険から受け取ることができる保険金の項目や相場については、以下の記事でも詳しく解説しています。
加害者が加入している自賠責保険に保険金を請求する流れや注意点については、以下の記事も参考になります。
3.被害者が利用できる被害者自身の保険

交通事故の被害者は、自身が加入している保険からも保険金を受け取ることができます。
特に加害者側からの支払いが滞っている場合や被害者自身の過失割合が高い場合には、自身の保険を利用することで一定の補償を受け取ることが可能です。
具体的には、以下のような保険を利用することができます。
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 車両保険
- 無保険車傷害保険
- 健康保険
- 労災保険
- 弁護士費用特約
順にご説明します。
(1)人身傷害保険
交通事故によって被保険者が怪我を負った場合に利用することができる保険です。
一般的には、被害者が加入する任意保険に特約として付されていることが多いです。
人身傷害保険では、怪我の治療費や傷害(入通院)慰謝料、休業損害などの損害項目について補償を受けることができます。
また、後遺障害等級の認定を受ければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益についても受け取ることが可能です。
人身傷害保険の大きな特徴は、過失割合の影響を受けずに契約で定められた基準に従って算定された保険金を受けることができる点にあります。
もっとも、人身傷害保険から受け取った金額は示談交渉において既払金として差し引かれることに注意が必要です。
人身傷害保険のメリットや利用の際の注意点については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(2)搭乗者傷害保険
交通事故によって被害者自身が怪我を負った場合や同乗者が怪我を負った場合に補償を受けられる保険です。
これも、人身傷害保険と同様、被害者が加入する任意保険に特約として付されていることが多いです。
人身傷害保険とは異なり、実際に生じた損害額にかかわらず、保険加入時に設定された金額を受け取ることができる点に特徴があります。
契約内容によって、受け取ることができる保険金は入院・通院に関する費用や後遺障害に関するものなどがあり、定額の支払いのみが受けられることに注意が必要です。
なお、示談交渉において、搭乗者傷害保険から受け取った保険金は差し引きの対象とはならない点も押さえておきましょう。
(3)車両保険
車両保険は、被害者自身の車の損害を補償するものです。
加害者が任意保険に加入していない場合には、人的損害については自賠責保険から補償を受けることができますが、物的損害については補償を受けることができません。
そのような場合に車両保険を利用することで、物的損害の補填を受けることができるのです。
また、加害者が任意保険に加入していた場合でも、被害者側にも過失がある場合には、過失分は被害者が負担しなければいけません。
そうすると、被害者側の過失が大きい場合には、車の損害額も大きくなるので、車両保険を利用した方が良いこともあります。
もっとも、車両保険を利用すると保険の等級が下がり、保険料が増額するというデメリットもあります。
そのため、車の損害が軽微である場合には、保険料の増額との兼ね合いから車両保険を利用せずに自己負担する方がメリットがある場合もあります。
車両保険の概要や利用の際の注意点については、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(4)無保険車傷害保険
無保険の車によって被保険者である被害者が死亡または後遺障害を負った際に利用できる保険です。
加害者が任意保険に加入していない場合はもちろん、加害者側の保険会社から保険金が支払われない場合や保険金だけでは損害全額を補填できない場合、相手方が不明の場合にも利用することができるところに特徴があります。
もっとも、被害者が死亡した場合や後遺障害を負った場合など、保険の適用対象が限定的である点にも注意が必要です。
加害者が無保険の場合の注意点や対処法については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(5)健康保険
先ほども述べたように、怪我の治療費については、加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側の保険会社が一括支払対応を行う場合がほとんどです。
もっとも、加害者が任意保険に加入していない場合や保険会社が支払いを拒否あるいは打ち切った場合などには、例外的に被害者が治療費を立て替え、示談交渉で請求する必要があります。
特に加害者の保険会社が行う治療費の一括支払対応はあくまで保険サービスの一環であり、保険会社の法的義務ではないため、支払いを拒否あるいは打ち切られた場合にこれを強制することはできないのです。
そのような場合には、健康保険を利用することで、自己負担分を軽減して治療を行うことができます。
もっとも、後述する労災保険が適用される事故については、健康保険を利用することができないため、注意が必要です。
交通事故の怪我の治療で健康保険を利用する際の注意点や必要な手続については、以下の記事を参照ください。
(6)労災保険
被害者が仕事中や通勤・退勤の際に交通事故に遭った場合には、労災保険から治療費や休業損害などの補償を受けることができます。
また、労災保険は、被害者側に生じる過失割合の影響を受けずに給付金を受け取ることができる点が大きな特徴です。
もっとも、労災保険を任意保険と併用すると、給付内容が重なるものについては支給調整が行われ二重で受け取ることができない点には注意が必要となります。
もちろん、労災保険と自賠責保険も、二重で受け取ることはできません。
労災保険から受け取ることができる給付金や利用する方法などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(7)弁護士費用特約
弁護士費用特約を利用することで、弁護士への相談料や弁護士費用について補償を受けることができます。
自動車保険のほか、火災保険やクレジットカードなどにも付帯されている場合があります。
また、被害者自身のものではなく家族の保険でも利用することができる場合もありますので、利用できる弁護士費用特約がないか一度確認してみるとよいでしょう。
保険内容によっても異なるものの、相談料は10万円、弁護士費用は300万円が上限となる場合が多いです。
弁護士特約を利用することで、費用負担を軽減しながら弁護士から専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。
特に交通事故では示談交渉や保険金の請求など、必要となる法的手続が多岐にわたります。
弁護士に相談することで、これらの手続を進めるためのアドバイスやサポートを受けることができ、示談交渉についても依頼することが可能です。
弁護士特約の概要や利用する流れについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
4.保険を利用する際の注意点

上記で紹介した保険を利用して保険金を受け取る際には、いくつか注意点があります。
具体的には、以下の点です。
- 過失割合によって受け取れる金額が減少するものがある
- 保険を利用できないケースがある
- 保険金の請求権には時効がある
それぞれについてご説明します。
(1)過失割合によって受け取れる金額が減少するものがある
過失割合は、事故の発生についての当事者の責任を割合で表したものです。
追突事故のようないわゆる「もらい事故」の場合は、被害者の過失はないとされるものの、それ以外の事故態様では被害者にも何割かの過失がつく場合が多いです。
被害者にも過失が認められると、その割合に応じて受け取ることができる保険金が減額されてしまうものがあります。
具体的には、加害者の任意保険や自賠責保険から受け取る保険金は、被害者の過失割合に応じて減額されてしまいます。
これは過失相殺と呼ばれるもので、賠償金の額に大きな影響があります。
そのため、加害者側の保険会社は支払う示談金を抑えようと被害者側の過失を高く見積もって交渉をしてくることが多いです。
したがって、示談交渉では、示談金額や損害項目だけでなく、過失割合についても自己に有利となるように交渉を進める必要があります。
過失割合に納得できない場合の対処法や弁護士に相談するメリットについては、以下の記事が参考になります。
(2)保険を利用できないケースがある
保険約款や契約内容によっては、保険を利用できないケースがあることにも注意が必要です。
例えば、事故の発生について被害者に故意または重大な過失がある場合などには、保険が使えないことがほとんどです。
また、被害者自身の保険については、交通事故の発生を保険会社に連絡するのが遅れた場合にも利用できないケースがあるため、注意が必要です。
それによって保険が使えないとなると、本来であれば受け取ることができるはずの保険金を請求することができなくなってしまうことになります。
そのため、交通事故に遭った場合には、警察への通報と合わせて自身の保険会社への連絡も併せて行うことが大切です。
保険金の請求のために保険会社に伝えるべき内容については、以下の記事も参考になります。
(3)保険金の請求権には時効がある
保険金を請求する権利には消滅時効があり、いつまでも請求できるわけではないことに注意が必要です。
具体的には、以下のように定められています。
| 加害者または加害者側の保険会社に対する請求 | 消滅時効の期間 |
| 怪我を負ったことに対する損害の請求権 | 事故発生日の翌日から5年 |
| 後遺障害を負ったことに対する損害の請求権 | 症状固定の日の翌日から5年 |
| 死亡による損害の請求権 | 死亡した日の翌日から5年 |
| 物の損害の請求権 | 事故発生日の翌日から3年 |
また、被害者自身の保険及び自賠責保険に保険金を請求する場合には、以下のように消滅時効の期間が設けられています。
| 被害者自身の保険会社に対する請求 | 消滅時効の期間 |
| 怪我を負ったことに対する損害の請求権 | 事故発生日の翌日から3年 |
| 後遺障害を負ったことに対する損害の請求権 | 症状固定の日の翌日から3年 |
| 死亡による損害の請求権 | 死亡した日の翌日から3年 |
| 物の損害の請求権 | 事故発生日の翌日から3年 |
そのため、時効期間にも注意しながら保険金の請求の手続を進める必要があります。
保険金の請求について不明な点などがあれば、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
まとめ
本記事では、交通事故の被害者が利用できる保険や受け取ることができる保険金の種類などについて解説しました。
加害者が任意保険に加入している場合には、原則として加害者側の保険会社に対して賠償を請求し、保険金を受け取ることになります。
もっとも、加害者が任意保険に加入していない場合や保険会社からの支払いが滞っている場合には、被害者ご自身の保険を利用することも検討する必要があります。
保険の利用や保険金の請求については、いくつか注意点もあるため、不安や疑問がある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
特に加害者側の保険会社に対して賠償金を請求する際には、弁護士に交渉を依頼することで、受け取れる金額が増額することが期待できます。
適正な賠償金を獲得するためにも、弁護士への相談・依頼が重要です。
弁護士法人みずきでは、これまで多くの交通事故の法的手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、交通事故に関する保険金についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事



































