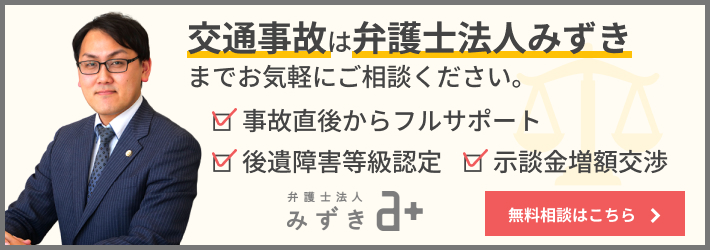交通事故の示談書を作成する際の注意点について弁護士が解説

「示談書とはどのような書類?」
「交通事故の示談書を作成する場合の注意点について知りたい」
交通事故の被害に遭って賠償を受ける際に示談書を作ると聞いて、このような疑問を抱く方もいるかもしれません。
示談書とは、当事者間での合意内容を明確にするために作成される書類です。
その目的は、後になって起こるトラブルを防ぐことにあります。
本記事では、示談書の記載事項や作成の際の注意点などについて解説します。
この記事を読んで、示談書を作成する際に着目するポイントについて押さえ、適正な賠償金の獲得につながれば幸いです。
1.示談書の概要

交通事故の被害者となった場合、加害者側から支払われる賠償金の額などの事項を決め、その内容どおりに賠償を受けることで、交通事故の問題は最終的な解決に至ります。
この場合、お互いの主張内容の争いが大きいときは訴訟等による解決が必要ですが、そうでなければ、賠償金の額などを話し合いで決めることによる解決を目指すことができます。
このような当事者間の話し合いによる解決のことを示談といい、示談によって合意した内容を書面にしたものが示談書となります。
ここでは、示談書がどういうものか、示談書を取り交わすメリット・デメリットなどについてご説明します。
(1)示談書とは
示談書とは、当事者間での合意内容をまとめた書面です。
交通事故の場合は、当事者間で話し合って決めた賠償金の額、支払方法、支払の期限、さらに過失割合などが記載されることになります。
示談は、第三者が介入せず、当事者間で解決するものです。
合意内容を証明するものがないと、一方の当事者が示談後にその内容と異なる主張をしてきた場合に、すでに示談した内容を証明することが難しくなってしまいます。
示談書は、このような事態を防ぐために作成しておく必要があります。
(2)示談書を作成するメリット
示談書を作成するメリットとして、以下のことが挙げられます。
- 後の紛争を防止できる
- 賠償金を支払ってもらいやすくなる
それぞれについてご説明します。
#1:後の紛争を防止できる
示談書を作成することで、示談後の紛争を防止することができます。
口約束では、示談内容を証明するものがないため、一方の当事者が示談での取り決めに違反して賠償金を支払わなかったり、示談で決めた内容と異なることを主張して内容を覆そうとしてきたりすることが考えられます。
しかし、示談書を作成していれば示談の内容を証明できるようになり、このような一方当事者の行動によって起こる示談後の紛争を防止することにつながります。
#2:賠償金を支払ってもらいやすくなる
示談した場合、いつまでにいくら支払うのか、分割であれば何回の分割で一回にいくらを支払うのかなどを決めて、これを示談書に記載します。
さらに、支払方法の取決めに従わなかった場合には、残りの賠償金を一括で支払うようにしたり、遅延損害金を支払うようにしたりすることも定めるようにします。
これらの事項により、賠償金を支払う側は示談内容を破った場合に一括での支払や遅延損害金の支払などのペナルティを受けることになりますので、これを避けるために取り決めどおりに支払おうとしやすくなります。
このように、示談書に定める事項によって、賠償金の支払を受けやすくなるという効果も期待できます。
(3)示談書を作成するデメリット
示談書を作成するデメリットとして、以下のことが挙げられます。
- 裁判所の判断を受けることができなくなる
- 後遺障害による賠償を受けられなくなる
それぞれについてご説明します。
#1:裁判所の判断を受けることができなくなる
示談をするとその後は争うことができなくなります。
示談は、法律上は当事者間での和解契約(民法695条)に当たります。
一度成立した契約は、詐欺や錯誤といった成立が難しい理由が認められない限り、後から覆すことはできなくなっています。
これにより、示談をした後に訴訟を起こしても、裁判所も示談内容に反した判断をすることができなくなるため、示談後は裁判所による客観的な判断を受けることができないということになります。
実際のところ、加害者の保険会社が提示してくる賠償金の金額は、訴訟をした場合に裁判所が認めるであろう金額よりも低額であるケースは多くあります。
しかし、一度示談をしてしまうと、あとからその内容を覆すことはできなくなりますので、示談内容が適切なものかどうかは慎重に判断する必要があります。
示談の内容に疑問がある場合は、示談に応じず、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
#2:後遺障害による賠償を受けられなくなる
示談書には、原則として示談で決めたもの以外に債権債務がないことを確認する条項(清算条項)を入れることになります。
そのため、後遺障害等級が認められるかもしれない症状があるのに、早く賠償を受けたいといった理由で後遺障害等級の認定を受けず、そのまま示談をしてしまうと、その後は後遺障害部分の損害(後遺障害慰謝料・逸失利益)について賠償を受けることができなくなってしまいます。
もっとも、この点については、後述するように留保条項を入れておけば、示談後も後遺障害部分の賠償を受けることができるようになります。
2.示談書の記載事項

示談書の形式については、法律で決められているわけではありません。
しかし、交通事故後の示談の場合、後のトラブルを防ぐために記載しておいたほうがよいという典型的な事項がいくつかあります。
ここでは、示談書に記載すべき事項についてご説明します。
(1)当事者の情報
当事者の情報として、氏名、住所などを記載します。
これらの情報を記載することで示談が誰と誰の間で行われたかを明確にします。
(2)事故の詳細
事故の情報として、事故発生日、事故発生時刻、事故発生場所、事故態様などを記載します。
これらの情報によって、その示談がどの事故によって生じた賠償金についての示談なのかを明確にします。
(3)示談の内容
交通事故後の示談では、賠償金の額、支払方法、支払期限、争いがあった場合には過失割合などを話し合って決めることになります。
このような、示談で決まった内容はしっかり示談書に記載しなければいけません。
支払方法でいえば、振込みなのか持参なのか、振込みであればどこの口座に振り込むのか、さらに一括なのか分割なのか、分割の場合は1回にいくら支払うかなどは記載することになります。
支払期限についても、令和〇年〇月〇日限りといったように明確に記載しておきます。
このように、示談内容を明確に記載し、次に説明する示談内容に違反した場合のペナルティも定めることで、示談後の紛争を防止することができます。
示談内容の記載があやふやだと、紛争防止の目的が達成できませんので、これはしっかりと記載する必要があります。
(4)示談金が取り決めどおりに支払われなかった場合の条項
分割支払の方法を定めたのにそのとおりに支払われなかった場合には、残りの金額を一括で支払うように定めたり(期限の利益喪失条項)、支払期限を過ぎてしまった場合には遅延損害金が発生することを定めたりといった、示談内容に違反した場合のペナルティを定めます。
これにより、相手が取り決めどおりに支払うことを促すことができます。
(5)清算条項
清算条項とはすでに説明したとおり、お互いに示談で取り決めたもの以外に債権債務がないことを確認するものです。
これがあることで、後からこれまで出てきていなかった事実を主張されるといったような事態を防止することができます。
3.示談書を作成する際の注意点

示談書を作成するにあたって、いくつか気を付けるべきことがあります。
ここでは、示談書を作成する際の注意点について説明します。
(1)当事者情報や示談内容に間違いがないかを確認する
当事者の情報、事故の詳細、示談内容が間違っていると、特定ができず、示談書を作成しても有効と認められない可能性があります。
そのため、各情報に間違いがないかをしっかり確認しましょう。
(2)後遺障害が生じる可能性がある場合には留保条項を設ける
示談後はその内容を争うことができなくなるため、基本的に示談は損害額が確定してから行います。
しかし、後遺障害等級が認められるような症状があるものの、休業損害の発生などにより当面のお金が必要で、後遺障害等級認定の前に賠償金を受け取りたいというケースも考えられます。
このような場合、後遺障害については示談の対象から除き、「後遺障害等級認定を受けた場合には別途協議する」といった内容の条項を加えて示談をすることで、先に傷害慰謝料や休業損害を受け取っておいて、後遺障害等級の認定や、認定を受けた場合の示談交渉については後回しにする、ということが可能になります。
4.示談書について弁護士に相談するメリット

示談書について弁護士に相談することで様々なメリットがあります。
ここでは、示談書を作成することになった場合に、弁護士に相談するメリットを説明します。
(1)賠償金の増額が期待できる
交通事故の示談では、慰謝料の算定基準として、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3つの算定基準が使用されます。
自賠責基準は被害者の最低限の補償を行うことを目的としており、これによって算出される賠償金の額は、3つの算定基準の中では最も低額となる傾向にあります。
また、算定基準が非公開となっている任意保険基準も自賠責基準と同程度か少し上回るものとされています。
そして、弁護士や裁判所が使用する裁判所(弁護士)基準によって算出される賠償金の額は、最も高額となりやすくなっています。
加害者側の保険会社は自賠責基準か任意保険基準を用いた金額で賠償金の提示を行うため、裁判所(弁護士)基準を用いた場合よりも低額であることがほとんどです。
弁護士に示談書について相談すれば、裁判所(弁護士)基準によって算定した賠償金の額での示談も可能になり、受け取ることができる金額の増額が期待できます。
(2)示談書に不備がないかチェックを受けられる
すでにご説明したとおり、交通事故における示談書の作成は必要な記載事項や注意点が多いです。
また、事案によっては、本記事で説明した内容以外にも記載しなければならない事項が出てくる可能性もあります。
被害者自身で、その交通事故の状況に最適な示談書を作成することは難しく、場合によっては示談内容が無効になってしまうリスクもあります。
その点、弁護士に相談すれば、事案の特殊性を踏まえた上で示談書に不備がないかのチェックを受けることができるので、リスクを回避して、最適な解決をすることができます。
まとめ
本記事では、示談書の記載事項や作成する際の注意点などについて解説しました。
示談書を一度取り交わすと、後から撤回することはできなくなってしまうため、示談書に署名する前に必ず内容を確認することが大切です。
反対に、示談書の内容に不備があると、示談が無効となり、被害者にとって不利な内容に修正されてしまうこともあります。
示談書の作成をスムーズに進め、適切な示談を行うためには、一度、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事