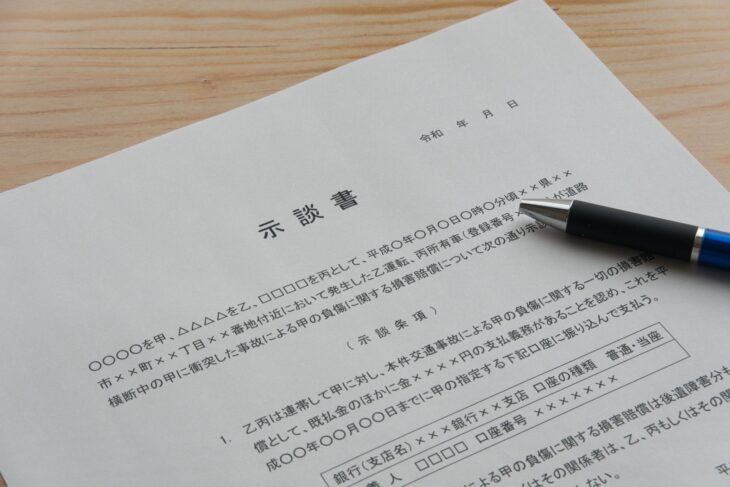後遺障害等級が非該当の場合の示談金はどうなる?受け取れる損害項目や非該当となる理由について解説
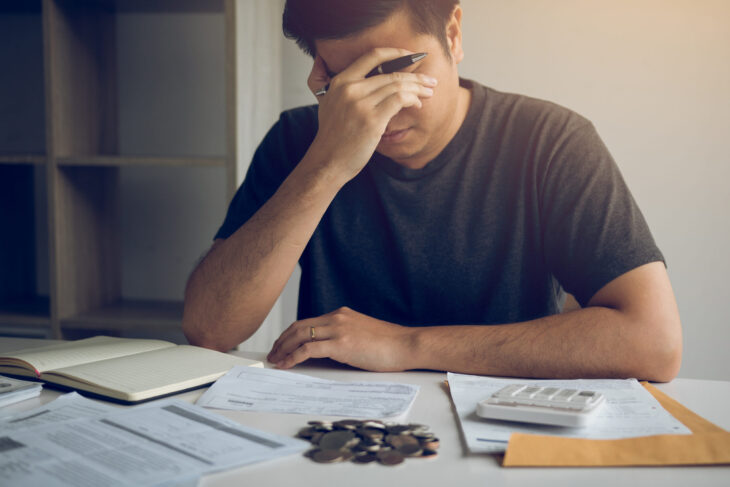
「後遺障害等級の認定を受けられなかったとき、示談金はどうなるのか」
「後遺障害等級が非該当となっても請求できる費用はあるのか」
後遺障害等級認定を申請したものの、非該当と判断された方の中には、示談金を受け取れるのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
実は、示談金とは損害賠償金のことで、その内容はいくつかの項目に分かれており、後遺障害等級が非該当となった場合でも、傷害慰謝料等の後遺障害にかかわらない損害項目について支払を受けることが可能です。
もっとも、非該当の場合は後遺障害に関する損害項目については受け取ることができなくなってしまい、その分示談金の金額は少ないものとなります。
本記事では、後遺障害等級が非該当になった場合の示談金の項目などについて解説します。
また、後遺障害等級が非該当となるケースや、非該当となった場合の対処法についても合わせて解説しています。
後遺障害等級が非該当となった後、どのような対応をしたらよいかとお考えの方の参考となれば幸いです。
1.後遺障害等級が非該当の場合に示談金は受け取れるのか

繰り返しになりますが、後遺障害等級が非該当の場合でも、示談金を受け取ることができます。
そもそも示談金とは、交通事故による損害賠償金のことを指しています。
したがって、被害者は損害が生じているのであればそれについての賠償金、つまりは示談金を受け取ることができます。
交通事故による損害は、怪我の治療費や通院交通費、傷害慰謝料、治療のために仕事を休んだことによる収入の減少(休業損害)といった怪我をしたことによって生じる損害(傷害に関する損害)、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害によって生じる損害(後遺障害に関する損害)、葬儀費用、死亡慰謝料といった被害者の死亡によって生じる損害、物的な損害などに分かれています。
このような損害のうち、後遺障害に関する損害については、後遺障害等級が非該当と判断された場合は、受け取ることができないものとなってしまいます。
後遺障害に関する損害である、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、後遺障害の等級によっては示談金の大半を占めるようになるケースもあります。
そのため、後遺障害等級認定を受けられた場合と非該当となった場合を比較すると、示談金の金額に大きな差が生じる可能性があることには注意が必要です。
なお、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の概要や相場については、以下の記事もご覧ください。
2.後遺障害等級が非該当となった場合でも受け取ることができる主な損害項目

後遺障害等級が非該当となった場合でも、傷害に関する項目と物損に関する項目については示談金として受け取ることができます。
傷害に関する項目で主なものは、以下のとおりです。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 入通院に関するその他の費用
- 休業損害
順にご説明します。
(1)治療費
治療費は、交通事故によって負った怪我の治療に要した費用を指します。
治療費の請求が認められるのは、発生した交通事故と怪我との間に因果関係が認められるものに限られます。
医師の診断を受けないまま時間が経過するなどしてしまうと因果関係が認められなくなってしまいますので、交通事故後に症状があるときは速やかに医師の診断を受け、その後も1か月以上の間を空けないように通院することをお勧めします。
本来、治療費については、被害者が負担し、治療の終了(治癒か症状固定の状態となったとき)後に加害者側へ請求していくのが原則となります。
ただし、加害者が任意保険に加入している場合、治療中も保険会社が直接病院へ治療費を支払う対応(一括対応)を行うのが一般的です。
この一括対応がされている限り、被害者が治療費を負担する必要はなくなります。
もっとも、被害者側の過失が大きい場合は、払い過ぎを防ぐために保険会社が一括対応を拒否することもあります。
また、一括対応を行うかどうかは保険会社の自由であり、法的な義務があるものではありません。
そのため、治療期間がある程度の長さになってくると保険会社が一括対応の打ち切りを言ってくることがありますが、この場合、被害者側が一括対応の延長を強制することはできないこととなっております。
加害者が任意保険に加入していない場合は、原則どおり、被害者がいったん治療費を立て替えて支払い、その後に請求を行う必要があります。
このとき、第三者行為による傷病届という書類を健康保険組合等に提出した上で健康保険を利用して自己負担額を減らすことができますし、加害者の自賠責保険や政府保障事業への請求により、治療終了前に治療費を回収できる可能性もあります。
いずれにせよ、加害者が任意保険に未加入の場合は、被害者が一時的に治療費を負担しなければならないことを想定しておきましょう。
治療費を立て替える必要がある場合やその際に利用できる保険などについては、以下の記事も参考になると思われます。
(2)傷害(入通院)慰謝料
傷害慰謝料は、交通事故によって怪我を負ったことに対する精神的苦痛を補償するものです。
傷害慰謝料の金額は、入通院の期間や日数を考慮して算定することになるため入通院慰謝料とも呼ばれています。
交通事故の損害額を算定する方法には自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3つがあり、傷害慰謝料もこれらに基づいて計算されます。
自賠責基準は被害者の損害について最低限度の補償を行うことを目的とした自賠責保険からの支払に用いられている基準であるため、最も低い金額が算出されやすいものとなっています。
任意保険基準は、任意保険会社が用いているもので、各保険会社で内容が異なり、詳細については非公開となっているものの、自賠責基準と同程度かやや上回る水準にとどまる額が算出されることが多いです。
これに対して、裁判所基準は裁判所が用いているものであり、金額が最も高額となりやすいものです。
したがって、傷害慰謝料について高い金額の支払を受けるためには、ほとんどの場合、裁判所基準を用いて請求をすることになります。
もっとも、被害者自身が保険会社に対して裁判所基準に従った請求をしても、これが認められることはほとんどありません。
裁判所基準での請求を保険会社に認めさせるためには弁護士から請求する必要がありますので、まずは裁判所基準での請求がいくらくらいになるのかなどを弁護士に相談するのがおすすめです。
なお、自賠責基準の算定方法や詳細については、以下の記事もご覧ください。
また、裁判所(弁護士)基準による算定方法や請求のポイントについては、以下の記事も参考になると思われます。
示談交渉を弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
(3)入通院に関するその他の費用
治療費や傷害慰謝料に加えて、入院や通院に付随して発生した費用についても加害者側に請求を行い、受け取ることが可能です。
具体的には、以下のような費用について補償を受けることができます。
- 通院交通費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 付添交通費
たとえば、入院時に必要な日用品の購入代、通院の際の公共交通機関の利用料、介護や介助にかかる費用などが該当します。
それぞれの具体的な算定方法や注意点については、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
(4)休業損害
休業損害とは、怪我が原因で仕事を休んだことによる収入の減少のことをいい、その減少分についても損害として加害者側へ請求することができます。
その金額は、原則として、収入の日額に休業日数をかけることで算定することになります。
ただし、休業損害についても、自賠責基準と裁判所基準とでは収入日額と休業日数の基準が異なることにより、金額が変わることがあります。
なお、自賠責基準による算定方法や請求の注意点については、以下の記事でも詳しく解説しています。
また、裁判所(弁護士)基準による算定方法やポイントについては、以下の記事も参考になります。
3.後遺障害等級非該当となる主な理由

後遺障害等級が非該当となった場合は、いくつかの理由が考えられます。
主に以下のような事実が非該当の理由となります。
- 症状についての他覚的所見がない
- 通院期間が短い・通院頻度が低い
- 症状に常時性がない
- 後遺障害診断書の記載内容に不備がある
後遺障害等級が非該当になると、前の項で触れたような損害項目の請求は認められるものの、後遺障害に関する補償を受けることはできません。
これから後遺障害等級の認定をこれから受けようと思っている方や、非該当と判断されてしまった方は、心当たりがないかチェックしてみましょう。
(1)症状についての他覚的所見がない
症状についての他覚的所見がまったくないと、非該当と判断されやすくなります。
例えば、むち打ち後の残存症状について、MRI検査によるヘルニア、脊柱管狭窄などの所見があるかどうか、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、深部腱反射検査等の神経学的検査の結果が陽性であるかどうかなどは、等級認定を受けられるかどうかに影響を及ぼすことになります。
そのほかにも骨折後の症状に対するレントゲン、CT撮影による所見の有無や、耳鳴り症状に対する聴力検査など、他覚的所見の有無はかなり重要な意味を持ちます。
このように、残存した症状ごとに必要な検査も違ってきますので、どのような検査が必要かどうかもわからないという場合には、交通事故事件、特に後遺障害事案の経験の豊富な弁護士に相談してみることをお勧めします。
(2)通院期間が短い・通院頻度が低い
通院期間が短い場合や、通院頻度が低い場合も非該当と判断される可能性があります。
後遺障害等級の認定申請は医師から症状固定(怪我の治療を一定期間にわたって継続した後に症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても改善しない状態)の診断を受けた後に行いますが、症状固定の判断がされるまでの治療の過程は後遺障害等級認定の審査においても重要となります。
一般的に、後遺障害等級の認定を受けるためには、最低でも6か月は通院していないと、その後も症状が残存するものと判断されなくなるといわれています。
そのため、通院期間が6か月に達していないにもかかわらず症状固定としてしまうと、後遺障害認定の確率はかなり低くなってしまいます。
また、むち打ち後の後遺障害の場合、月に数回程度しか通院していないときは、症状が軽度のものであったと判断されて、これもその症状が後遺障害として残存していくものと判断されなくなってしまいます。
さらに、整骨院への通院が多い場合も、医師の診察に基づいて通院をしているわけではない、と判断されて不利な影響を受けてしまいます。
むち打ちの場合は、少なくとも3日に1回程度くらいの頻度で整形外科へ通院しておく必要があるでしょう。
(3)症状に常時性がない
後遺障害等級認定を受けられる症状は、常に生じているものである必要があります。
たとえば、気温が低いとき、長時間同じ姿勢でいたとき、運動をしたあとなどに生じる症状については、非該当となりやすくなってしまいます。
(4)後遺障害診断書の記載内容に不備がある
後遺障害診断書の記載内容に不備がある場合も後遺障害等級が非該当となることがあります。
後遺障害等級認定の手続は、原則として提出された書面・資料の審査によって行われます。
後遺障害診断書は、症状固定の診断を受けた後に医師が作成する書類であり、後遺障害の症状や他覚的所見の有無が記載される、等級認定の審査においてもっとも重要なものです。
この後遺障害診断書の記載内容によって後遺障害等級の認定が決まるといっても過言ではありませんので、内容について不備がないかよく確認する必要があります。
たとえば、以下のような記載内容になっている場合には、等級非該当となる可能性が高いです。
- 症状に常時性がみられない(気温が低かったり、天気が悪かったりすると症状が出るなど)
- 行われた検査(CT検査、MRI検査といった画像検査、ジャクソンテスト、スパーリングテストといった神経学的検査など)の結果が記載されていない
- 今後の見通しについて「完治」や「緩解の見込みあり」などの記載がされている
(1)から(3)までに挙げたような事情があると認められてしまう記載になっていないか、症状が今後も持続していくものとされているか、注意する必要があります。
後遺障害診断書の記載内容のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
4.後遺障害等級に非該当となった場合の対処法

後遺障害等級に非該当となった場合でも、いくつかの対処法が考えられます。
主な対処法は以下のとおりです。
- 弁護士に相談する
- 異議申立てを行う
- 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請を行う
- 訴訟を提起する
順にご紹介します。
(1)弁護士に相談する
後遺障害等級に非該当となった場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、等級非該当となった理由や原因について分析・説明を受けることができます。
また、症状の内容や程度などから、等級認定を受けられる可能性があるかについても説明を受けることができ、そのような場合には必要な手続を依頼することも可能です。
弁護士に相談することで、後遺障害診断書の記載漏れなど、対処できる可能性のある非該当の原因が見つかる場合もあります。
後遺障害等級の認定を受けるために重要なポイント等を把握しているので、ご自身で申請したものの等級非該当になった方は、弁護士に相談してみましょう。
(2)異議申立てを行う
異議申立ては、後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構に対して再審査を請求する手続です。
異議申立てを行う期限や回数に制限はないため、理論上は何度でも行うことが可能です。
もっとも、認定を行う機関に対する再審査請求であることから、ただただ回数を重ねても意味はありません。
後遺障害診断書の修正や医師の意見書など、非該当の認定を覆すに足りる資料を追加提出することが重要なのです。
後遺障害診断書の記載内容を再確認し、もう少し具体的に後遺障害の症状を証明できる余地がないか探してみましょう。
異議申立ての流れや注意点などについては以下の記事もご参照ください。
(3)自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請を行う
自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関に審査を申請することもできます。
これは、自賠責保険での異議申立てを経た場合に活用することができる制度です。
審査には、自賠責保険に対する異議申立て後に新たに検査した画像や検査結果、診断書や意見書も提出することができるようにはなっています。
しかし、紛争処理機構が行うのは、損害保険料率算出機構の判断が適正であるかどうかの審査であり、また、この審査は異議申立てとは異なって1度しか申請を行うことができないものです。
そのため、新たな資料が大量に出てきている場合には、それらも提出して再度の異議申立てを行い、これにも不服があったら紛争処理機構への申請をするというように、タイミングを考える必要があります。
申請の手続の流れやポイントについては、以下の記事も参考になるので、合わせてご参照ください。
(4)訴訟を提起する
最終的に裁判所に訴訟を提起し、認定されるべき後遺障害等級相当の損害賠償を請求する方法もあります。
裁判所は、損害保険料率算出機構や紛争処理機構の審査結果に拘束されることはなく、客観的な証拠に基づいて独自に判断をするため、異議申立て等の結果に囚われない判断がされる可能性はあります。
ただし、損害保険料率算出機構等の審査結果に拘束されないとはいっても、これらの結果はかなり尊重されるものとなってしまっているため、有効な証拠を提出してこれを覆していくのは容易ではありません。
異議申立て等が良い結果となっていない場合に、訴訟でこれを覆すには少なくとも十分な検討や事前の準備が必要ですので、弁護士のサポートを受けることが重要です。
まとめ
後遺障害等級が非該当になっても示談金を受け取ることは可能です。
ただし、後遺障害等級の認定結果に応じて請求できる後遺障害慰謝料等を受け取ることができず、金額は少なくなってしまいます。
後遺障害等級が非該当になる理由はいくつか考えられます。
もし審査機関から非該当の通知を受けたとしても、これを覆せる可能性があるかもしれません。
まずは弁護士に相談して、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、後遺障害等級に関する相談を無料で受け付けておりますので、非該当の認定を受けた方も諦めずにご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事