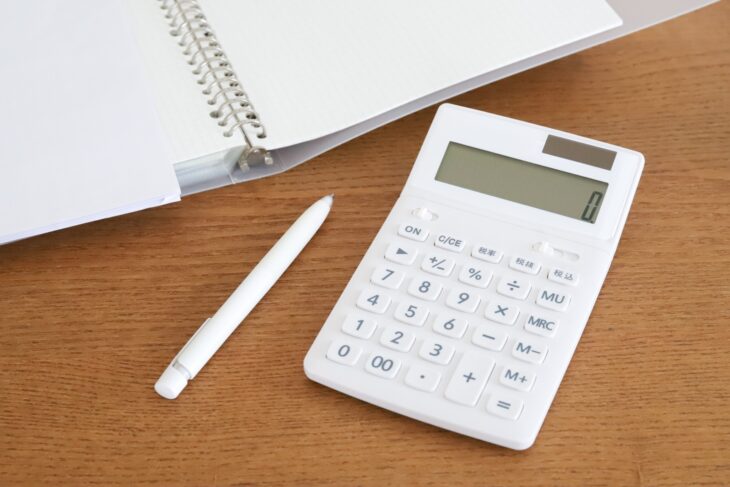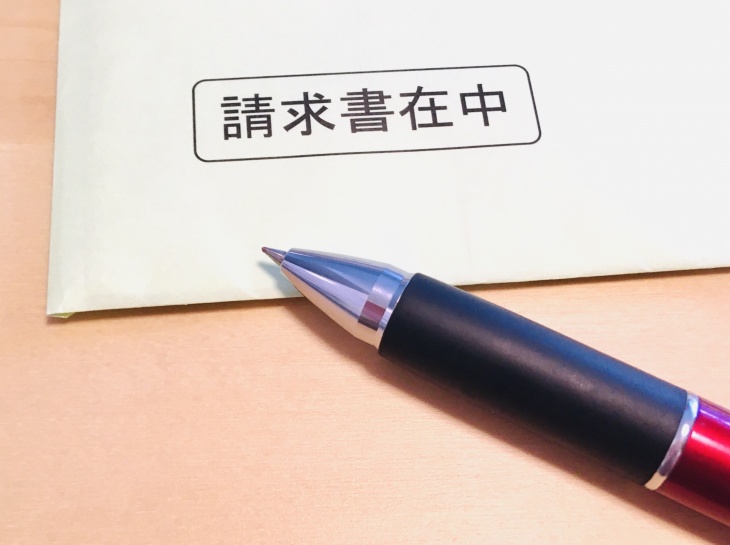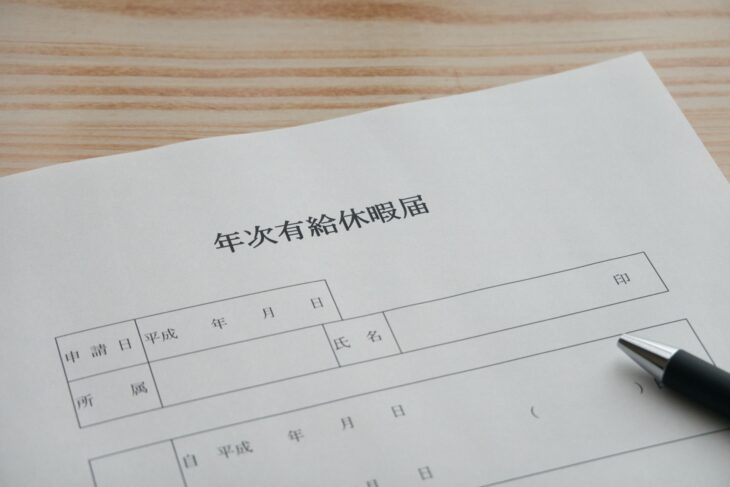休業損害を個人事業主が受け取ることができるのか弁護士が解説

「個人事業主でも休業損害を受け取ることはできる?」
「休業損害を請求する際に必要なものや注意点を知りたい」
交通事故に遭ってしまった個人事業主の方にとっては、事故による怪我で仕事を休まざるを得なくなった場合の休業損害を賠償してもらえるかどうかが気になることと思います。
結論として、個人事業主の休業損害についても請求することができますが、給与所得者に比べて計算等が複雑になる傾向にあります。
本記事では、個人事業主の休業損害の算定方法や必要書類、請求の際の注意点などについて、適宜給与所得者との違いに触れながら解説します。
この記事を読んで、個人事業主の休業損害の算定のポイントや注意点を把握し、適切な対応を行うための参考となれば幸いです。
1.個人事業主と休業損害

個人事業主の方でも休業損害を請求することはできます。
もっとも、個人事業主の場合、よく見られる給与所得者の場合と異なる点が多いです。
給与所得者の場合、月収や日給が固定されていることが多く、また、勤め先の会社がその人がいつ休んだか証明することも容易ですので、減収がいくらであったかを計算・証明することは比較的容易です。
他方で、個人事業主の場合、収入に変動がある上、いつ仕事をしていつ休んだのかを証明する会社などがありませんので、そもそも本来いくらの収入があったとすべきなのか、休んだことによる減収がいくらになるのかを証明することは必ずしも容易ではありません。
ここでは、休業損害とはどういったものなのか、個人事業主が休業損害を請求するために必要なことは何かについてご説明します。
(1)休業損害とは
休業損害とは、交通事故で怪我をしたことによって仕事ができなくなり、収入が減った場合の減少額のことです。
その金額は、「収入の日額×休業日数」で算定します。
個人事業主は、給与所得者のように会社から給料が出ているわけではありませんが、仕事ができなくなることで収入が減ることはありますから、当然、休業損害を請求することはできます。
(2)休業損害が認められるための条件
ここでは、個人事業主の休業損害の請求が認められるためにはどのような条件が必要なのかについてご説明します。
- 休業による減収があること
- 休業の必要性
#1:休業による減収があること
休業損害は、仕事を休んで減少した収入分の損害のことです。
そのため、仕事を休んだとしても減収がなければ休業損害は認められません。
たとえば、賃貸物件を管理している人が、事故による怪我に管理業務を行えなくなったとしても賃料収入がそのまま入ってきているのであれば休業損害は発生していないことになります。
また、収入に変動がある事業をしていて、たまたま事故後に収入が減少していただけという場合も、休業損害は認められないでしょう。
ただし、減収がない場合でも、減収を生じさせないために代わりの人を雇って事業を続けたというときには、代わりの人に支払った費用の請求が認められる可能性があります。
#2:休業の必要性
休業による減収があったとしても、そもそも休業の必要性がなければ休業損害の請求は認められません。
たとえば、怪我が軽微で働くことが十分可能であったのに自己判断で休業したために減収が生じたという場合、休業損害の請求は否定されてしまうことになるでしょう。
このようなことにならないよう、休業の必要性があるかどうかは医師に相談して確認する必要がありますし、可能であれば意見書等に必要性を記載してもらう、といった対策が必要となります。
(3)個人事業主が休業損害を請求する際に必要となる書類
ここでは、個人事業主が休業損害を請求するために必要な書類についてご説明します。
- 収入に関する資料
- 休業に関する資料
#1:収入に関する資料
すでにご説明したとおり、休業損害の算定をするためには収入の日額がいくらかという情報が必要になります。
そして、収入の日額は、事故の直近の収入から計算することになります。
個人事業主の収入の資料は確定申告書ですから、個人事業主が休業損害を請求する際には、事故前年の確定申告書が必要となります。
季節や月によって売上げの増減が激しく、年間の売上げからでは休業期間中の損害額を算定することが難しいような場合には、さらに月ごとの売上げの資料が必要となることもあります。
また、事業を始めたばかりで確定申告を行っていない時期に事故に遭ったという場合には確定申告書がありませんので、直近の売上げが記録された会計帳簿、出納帳、預金の取引履歴などによって、収入を証明することになります。
#2:休業に関する資料
すでにご説明したとおり、休業損害が認められるためには、休業の必要性があったことを証明する必要があります。
休業の必要性があるかどうかの判断には怪我の程度に加え、業務の内容もかかわってきます。
そこで、まずは骨折、脱臼、固定の必要があるかどうかなど、怪我の内容を証明するための診断書や、安静にするために休業の必要性があるとする医師の意見書などがあるとよいでしょう。
さらに、業務の内容が肉体労働であるために休業の必要があるような場合には、そのことを証明する資料として、業務の日報等の提出も考えられることになります。
2.個人事業主の休業損害の算定方法
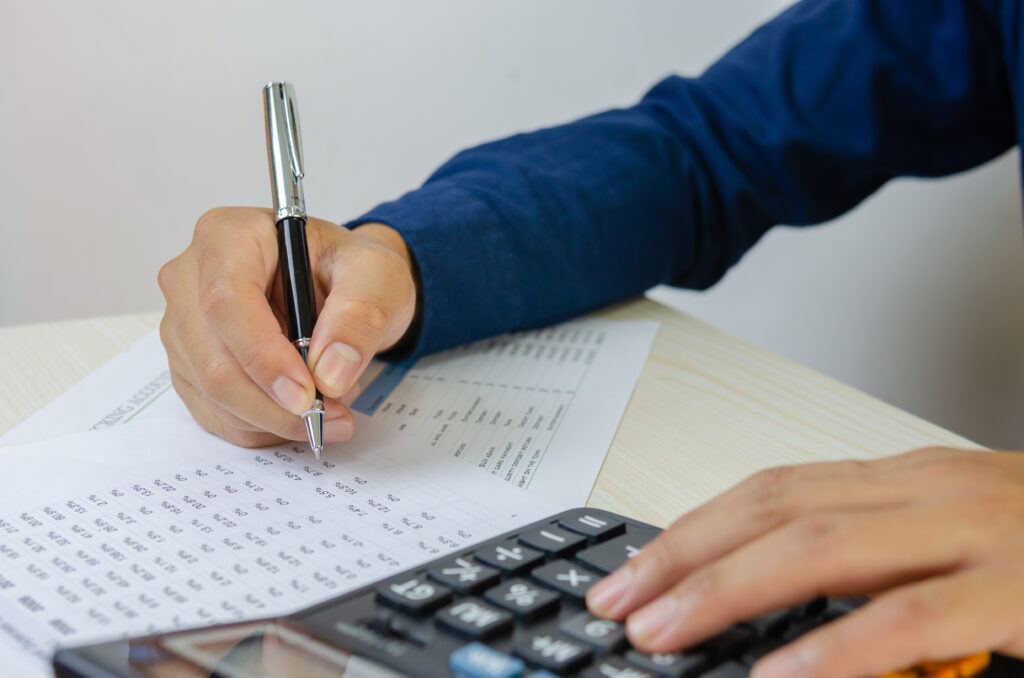
個人事業主の場合、休業損害の計算方法は給与所得者とは異なります。
ここでは、個人事業主の休業損害の算定方法についてご説明します。
(1)自賠責基準
自賠責基準とは、交通事故の被害者に最低限補償される金額を算定する基準で、自賠責保険会社から休業損害が支払われる際に使用されます。
具体的な算定基準は、「日額6,100円×休業日数」であり、休業日数は通院日数がそのまま使われることが多いです。
つまり、10日間通院した場合には、6,100円×10日=61,000円が休業損害額となります。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている基準です。
算定基準は、任意保険会社ごとに異なっており、非公開とされていますのでいくらが算定されるかを正確に予測することは困難です。
ただし、任意保険会社からは、自賠責基準と同等か、これをわずかに上回る程度の金額が提示されることが多いです。
(3)裁判所(弁護士)基準
裁判所基準といっても、休業損害については自賠責保険のような金額の基準があるわけではありません。
裁判所が判断するのと同じように、証拠から収入の日額および休業日数を証明して、休業損害の金額を主張していくことになります。
そのため、事案に応じて算定方法が異なって証明が難しいこともあるものの、事実に即した金額を賠償してもらえる可能性が高くなります。
3.裁判所基準で個人事業主の休業損害を算定する際の注意点

裁判所基準は、事案に応じて査定方法が異なるため、いざ自分の休業損害を算定しようとすると、どのように算定すればよいかわからないことも多いと思います。
そこで、ここでは裁判所の考え方に従って個人事業主の休業損害を算定する際の注意点を代表的なケースごとにご説明します。
(1)基礎収入の算出方法
1日あたりの基礎収入は、所得金額に固定経費を加算した金額です。
所得金額は、事故前年度の年間所得を365日で割った金額になります。
年間所得は、原則として確定申告の際に申告した所得金額が用いられます。
給与所得者であれば、月ごとの所得はあまり変わらないため、事故前3か月分の給与を稼働日数又は90日で割った金額となります。
しかし、個人事業主は給与所得者に比べて月ごとの所得の変動が激しいため、年間所得を365日で割って算定します。
固定経費は、休業しても支払い続けなければならない費用のことです。
例えば、事業所などの家賃、水道光熱費の基本料金部分、税金といったものが挙げられます。
これらは、休業した後に事業を継続するために休業中も支出が必要ですが、それによる対価が得られない無駄なものとなってしまうため、交通事故による休業損害の一部と考えられます。
一方で休業したことにより支払わなくてもよくなった流動経費は、損害には含まれません。
#1:確定申告をしていなかったケース
確定申告をしていない場合でも、通帳や帳簿、領収書等で所得や減収を証明することができれば、休業損害を請求することができます。
ただし、申告をしていないのに収入があると主張することは、一種の矛盾主張となりますので、その立証のハードルはかなり高いものと考えるべきです。
#2:実収入が確定申告書よりも多かったケース
この場合には、原則として、確定申告書に記載されているとおりの金額しか基礎収入にできません。
通帳や帳簿から実収入が証明できれば、実収入が基礎収入として認められることもありますが、そのハードルの高さについては申告をしていなかった場合と同様です。
#3:増収が見込めていたケース
この場合、事故前年の年間所得で算定すると、実際の減収額と異なってしまいます。
そのため、増収可能性を証明することで増収分の休業損害を請求できる可能性があります。
#4:夫婦で経営していたケース
夫婦で一緒に経営していた場合、被害者一人の所得とはいえないため、被害者以外の寄与分(所得に貢献した割合)を除いて、年間所得を算定します。
#5:赤字経営だったケース
事故前から赤字経営だった場合でも、事故によって赤字が拡大したといえる場合には、その拡大部分を損害として、休業損害を請求できる可能性があります。
また、赤字であったとしても、休業によって固定経費が無駄になってしまうのは変わらないため、固定経費を休業損害として請求できる可能性があります。
(2)休業日数の考え方
仕事を休んだ日がすべて休業日数として認められるわけではなく、事故による怪我やその治療のために休まなければならなかった日、つまり休業の必要性があった日に休んだ場合に休業日数に含まれることとなります。
そのため、怪我の軽重だけでなく、怪我をした場所や職業によっても休業の必要性の有無は異なります。
例えば、同じ足を怪我した場合であっても、建築業等の肉体労働を主としている人と、プログラマーなどのデスクワークを主としている人では前者の方が休業の必要性が認められやすい、といえるでしょう。
4.休業損害を請求する方法と流れ
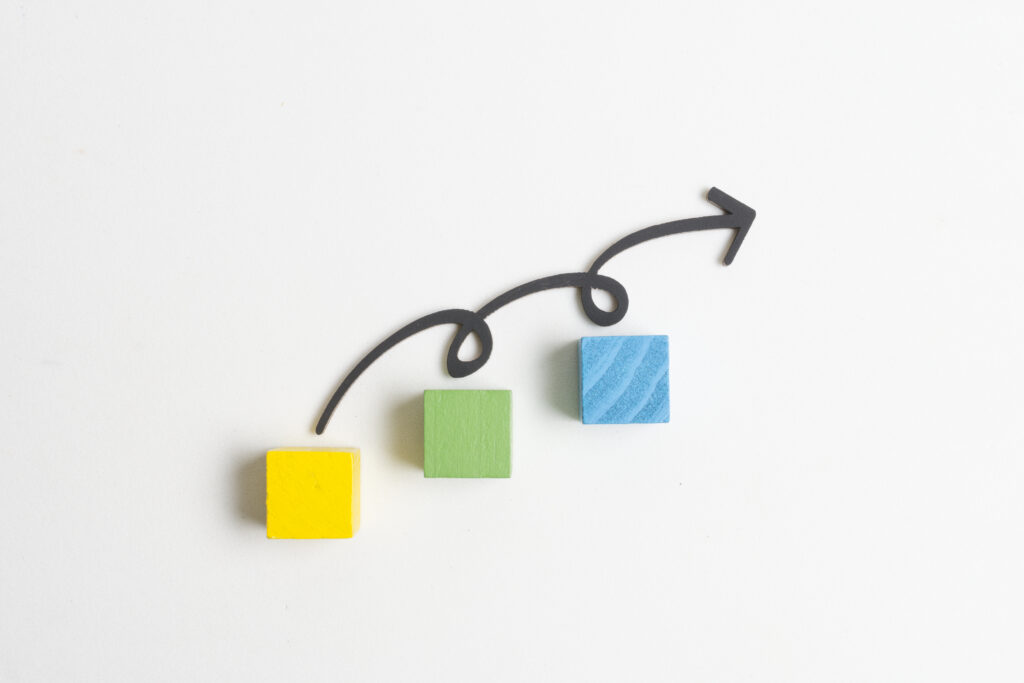
次に、個人事業主が休業損害を請求する流れについてご説明します。
(1)被害者請求
被害者請求とは、自賠責保険会社に被害者自身が保険金を請求することをいいます。
被害者請求をする場合には、請求に必要な書類を集めて、加害者の自賠責保険会社に提出します。
自賠責保険会社に提出された書類は調査事務所という第三者機関に送られ、そこで調査が行われます。
この調査により休業損害があると認定されれば、休業損害が支払われます。
なお、自賠責保険会社への請求の場合、自賠責基準で算定された金額の支払となります。
また、被害者請求により支払を受けた休業損害は、のちの示談交渉の際、既払金として控除されることになります。
(2)内払い
内払いとは、加害者の任意保険会社から、治療が終了する前に休業損害を前払いしてもらうことをいいます。
まず、休業損害の請求に必要な書類を集めて、相手方保険会社に提出します。
その後、内払いの可否とその内容を交渉します。
なお、最終的に賠償金を支払ってもらう際、内払いで支払ってもらった金額については、被害者請求で受け取ったものと同じく既払金として控除されます。
そのため、内払いを受けても受けなくても最終的に受け取れる金額に差はありません。
(3)示談交渉
休業損害の請求に必要な書類を集めて、休業損害額を算定します。
示談交渉では、休業損害以外の慰謝料や治療費なども含めたすべての損害賠償額を算定することになります。
そして、相手方に損害賠償額を提示し、相手方に対案を求めます。
その対案が希望額に達していなければ交渉して、納得できる金額が出てきたら示談に応じることになります。
まとめ
本記事では、個人事業主の休業損害の算定のポイントや注意点などについて解説しました。
個人事業主が休業損害を請求し、受け取るためには様々な注意点があります。
スムーズに手続を進めるためには、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事