交通事故の示談とは?流れや弁護士に依頼するメリット

「交通事故の示談ってどんなことをするのか」
「交通事故後から示談までどんな流れで進むのか」
交通事故の被害に遭った方の中には、交通事故の示談がどのように行われるのか気になっている方もいると思います。
交通事故の示談は、交通事故の当事者双方の合意によって賠償問題を解決する方法です。
もっとも、示談の流れやポイントを把握していなければ、被害者にとって不利な条件で示談が成立してしまうリスクがあります。
本記事では、交通事故の示談の流れや弁護士に依頼するメリットについて解説します。
被害者の方が示談交渉を有利に進め、適正な賠償金を獲得するための参考となれば幸いです。
1.示談の概要

示談ではどのようなことを決めるのか、どのくらいの期間で決着がつくのかなどを把握しておくことは、示談交渉をスムーズに進める上でも重要です。
以下では、交通事故における示談の概要や示談で決めることなどについてご説明します。
なお、交通事故の示談交渉の意義については、以下の記事も参考になります。
(1)示談とは
示談とは、当事者の話し合いによって交通事故の賠償問題を解決する方法です。
具体的には、交通事故による修理費用や怪我の治療費、慰謝料、休業損害などの損害について確定し、その金額を定めます。
交通事故のトラブルは当事者同士で解決するのが基本ですが、加害者が保険に加入している場合は、被害者と加害者側の保険会社の間で行われます。
示談が一度成立すると、その内容に法的拘束力が生じるため、その内容を後から撤回することはできません。
示談内容に疑問や納得できない点があれば、安易に応じず、弁護士などの専門家に相談しましょう。
なお、示談交渉を被害者自身で行うリスクと弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
(2)示談で決める内容
示談では、当事者間でさまざまなことについて話し合います。
主な項目は、以下のとおりです。
- 過失割合
- 示談金
順にご説明します。
#1:過失割合
過失割合は、交通事故の発生について、被害者と加害者にどの程度の責任があるかを数値で示したものです。
被害者の過失の割合に応じて示談金額が変動するので、被害者に何らかの過失が認められれば、受け取ることができる賠償金は減額されてしまいます。
適切な過失割合を主張するには、ドライブレコーダーや物損資料、刑事記録などの客観的な証拠に基づいて、適切に反論・立証することが求められます。
過失割合について示談交渉が難航する原因と対処法については、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
#2:示談金
示談金は、交通事故によって生じた損害を解決するために支払われるお金のことです。
示談金の中には、怪我の治療費や入院・通院によって仕事を休まなければならなくなった際の収入の補填など、さまざまな項目が含まれています。
日常生活でも耳にすることのある「慰謝料」は、被害者に支払われる示談金の項目の一部です。
具体的な示談金の項目や算定方法については、次項で詳しく解説します。
なお、示談金の概要や相場観などについては以下の記事もご参照ください。
(3)示談に要する期間
示談は、交通事故の最終的な解決を図ることです。
そのため、損害の総額が判明してから交渉を行うことになります。
事故発生から示談が成立するまでの期間は、事故態様や怪我の有無、程度などによって変動します。
たとえば、人身損害がない物損事故の場合で、特に争点のないときは、車両等の修理費用が確定してから示談交渉を開始するため、交通事故から2~3か月での示談成立が目安です。
また、人身損害が生じた事故の場合は、被害者の怪我が治癒するなど治療が終了した後で、示談交渉を開始することになります。
治療にどの程度の期間を要するかによりますが、治療終了から2~3か月程度を要することが多いです。
そのため、例えば半年治療を行った場合には、事故日から9か月ほどかかることが見込まれます。
後遺障害が残った場合には、後遺障害等級の申請手続きも必要となるため、さらに時間がかかる傾向にあります。
後遺障害が認定されるまで2~6か月程度かかるため、そのぶん解決まで時間がかかると思っておきましょう。
当事者間で過失割合や示談金の項目の有無、金額などについて争いがある場合には、交渉が難航するケースもあり、示談交渉が長引くこともあります。
なお、以下の記事で、示談交渉が長引く原因と対処法について解説していますので、合わせてご参照ください。
また、示談交渉を早期に終わらせたい場合のポイントや注意点については、以下の記事も参考になります。
2.示談金の主な内容

示談金の項目は、大きく分けると4つあります。
- 物が壊れたことによる損害
- 怪我による損害
- 後遺障害による損害
- 死亡による損害
示談金の項目と算定基準については、以下の記事でも詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。
(1)物が壊れたことによる損害
物が壊れた場合、そのものの時価や修理金額が賠償の対象となります。
交通事故による怪我がない場合であっても、物損について保険会社に請求し、受け取ることができます。
怪我と車両の損壊の双方の被害がある場合には、先に物損のみについて示談交渉を進めることが一般的です。
なお、物損の示談交渉のポイントについては、以下の記事が参考になります。
(2)怪我による損害
怪我による損害には、以下のような項目が含まれます。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 通院交通費
- 休業損害
順にご説明します。
#1:治療費
治療費は、交通事故による怪我の治療に要した入通院費用のことをいいます。
多くの場合、一括対応と言って、加害者側保険会社が直接病院へ支払いますが、被害者が治療費を立て替えた場合には、示談金として請求することになります。
なお、治療費を受け取る際の注意点などについては以下の記事も参考になりますので、ぜひご参照ください。
#2:傷害(入通院)慰謝料
傷害(入通院)慰謝料は、交通事故を原因として怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
入通院の期間に応じて算定され、採用される算定基準によって金額が変わります。
この基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3タイプがあり、一般に、裁判所(弁護士)基準が、被害者にとって最も有利な金額となります。
加害者側の保険会社は、任意保険基準を使って慰謝料を算出しますが、弁護士に示談交渉を依頼することで裁判所(弁護士)基準を用いた交渉を行うことになります。
自賠責基準、裁判所(弁護士)基準による算定方法と相場の比較については、以下の記事も参考になります。
#3:通院交通費
通院交通費は、交通事故による怪我の治療のための入通院に要した交通費です。
公共交通機関を利用して通院した場合、バスや電車の料金を請求することができます。
ただし、交通費の発生が交通事故によるものであることを証明するほか、必要かつ相当な支出であることが認められなければなりません。
たとえば、徒歩で行ける範囲なのにあえてバスや電車を使ったり、バスや電車で通院できるにもかかわらず、あえてタクシーを利用したりした場合には、相当性のない出費ととらえられ、通院交通費として認められない可能性があります。
なお、通院や入院に関するそのほかの費用や算定方法については、以下の記事もご参照ください。
#4:休業損害
休業損害は、事故による怪我のために欠勤や早退等をせざるを得なくなり、それによって収入が減少した際の補償です。
職業によって算定方法が異なるため、サラリーマンなのか事業主なのかという点を踏まえて、適切に計算する必要があります。
また、専業主婦(夫)や学生でも請求できることがあります。
休業損害の算定方法やポイントについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(3)後遺障害による損害
怪我の治療を一定期間にわたって継続した後、症状が一進一退となると治癒又は症状固定の診断を受けることになります。
この時点で残存している症状の内容や程度によっては、申請を行うことで後遺障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害等級には16の等級があり、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益等を受け取ることができるのです。
#1:後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、症状固定時において後遺障害が残っている場合に受けた精神的苦痛に対する補償のことをいいます。
どの算定基準を採用するか、認定される後遺障害等級が何かによって金額が変動します。
算定基準には、傷害慰謝料と同様、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3タイプがあります。
このうち、自賠責基準は、被害者の損害の最低限度の補償を目的としているため、その相場は低額であり、任意保険基準も同程度の金額にとどまります。
なお、後遺障害慰謝料の相場については、以下の記事にまとめていますので、併せてご参照ください。
#2:後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって、事故前と同様の労働を行うことができなくなってしまい、収入が減少することに対する補償です。
後遺障害逸失利益の算定式は、以下のように定められています。
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
法令により、認定される等級に応じた労働能力喪失率の目安が定められています。
もっとも、労働能力喪失率は、最終的には、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の内容等を考慮して判断されるため、必ずしもその目安のまま認められるわけではありません。
適切な金額を算定するためにも、示談交渉で後遺障害の内容や程度が仕事や生活に及ぼす影響を具体的に主張・立証していくことが重要です。
なお、後遺障害逸失利益の概要や受け取るためのポイントについては、以下の記事もご覧ください。
(4)死亡による損害
被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀関係費用等を請求することができます。
死亡事故の場合、相続が関係してくるため、誰が何を請求できるか迷ってしまうことも珍しくありません。
請求に漏れがないように、しっかりと確認しながら進めていく必要があります。
死亡に関する損害の金額相場や請求の流れについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
3.示談の流れ
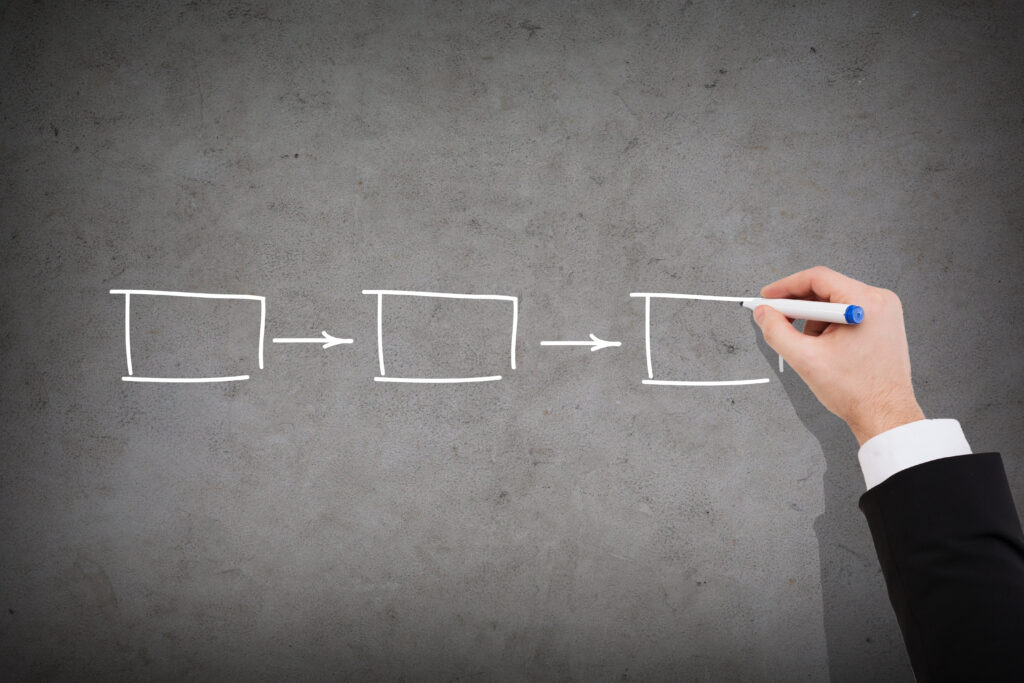
交通事故の発生から示談成立までの流れは、以下のとおりです。
- 交通事故の発生
- 医療機関を受診
- 後遺障害等級の認定手続
- 保険会社からの示談案の提示
- 示談交渉
- 示談書の取り交わし・示談金の受け取り
順に解説します。
(1)交通事故の発生
交通事故に遭った場合は、速やかに警察に届け出ることが重要です。
警察に対して交通事故の発生を届け出ることは道路交通法上の義務であるため、怪我などの外傷がない場合や軽微な事故であっても、必ず届け出る必要があります。
もし警察への届出を怠れば、道路交通法上の義務違反となるほか、交通事故が発生したこと自体を証明できなくなる可能性が高いです。
加害者側に警察に届出をしないように提案されても、必ず警察に届け出ましょう。
なお、警察への届出とあわせて保険会社への連絡もこの時点で行うことが重要です。
さらに、加害者にも加害者が加入している保険会社への連絡を依頼しておきましょう。
加害者側の保険会社への対応の流れや注意点については、以下の記事にまとめていますので、併せてご確認ください。
なお、加害者側の保険会社が分からない場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
(2)医療機関を受診
警察への対応が済んだら、医療機関を受診しましょう。
軽度の事故で、目立った外傷がない場合でも、整形外科などの医療機関を速やかに受診することが重要です。
また、交通事故直後は、興奮状態によって身体の異常に気づかないことがあるので、すこし時間が経ってから痛みや痺れなどの症状が現れた場合には、すぐに受診しましょう。
事故と受診の間に時間が経てば経つほど、事故による怪我なのかの判断が難しくなってしまい、賠償の対象にならない可能性が高まりますので、症状を感じたらすぐに受診するように心がけましょう。
また、治療を開始したら、医師の指示に従って適切な頻度と期間にわたって通院することが大切です。
通院頻度が極端に少なければ、加害者側から軽傷と判断され、賠償金が減額される可能性があります。
症状固定の意義や目安となる期間などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
(3)後遺障害等級の認定手続
一定期間にわたって治療を継続した後に症状固定となった場合には、残存している症状の内容や程度によって、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、後遺障害に関する賠償金を受け取ることができます。
申請方法には、加害者側の保険会社に手続を依頼する事前認定と被害者自身が手続を行う被害者請求の2つがありますが、適切な等級の認定を受けるために、審査機関に詳細な情報を自己の判断で提供できる被害者請求を行うことがおすすめです。
それぞれの特徴や注意点については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
(4)保険会社からの示談案の提示
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社から示談案が提示されることが一般的です。
任意保険会社は任意保険基準を用いて慰謝料等の算定を行うため、自賠責基準で算出した場合と大きな差はなく、低額にとどまることがほとんどです。
保険会社が提示する示談金は、増額する余地があることが多いため、安易に示談書に署名・捺印をしないようにしましょう。
少しでも納得がいかないと感じたら、保険会社の提案を鵜呑みにするのではなく、冷静に検討することが大切です。
なお、保険会社から連絡が来た場合の対処法のポイントについては、以下の記事をご参照ください。
また、提示された示談金が低額であった場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
(5)示談交渉
保険会社が提示した示談案に納得できない場合は、示談金の引き上げや過失割合の見直しなどを交渉しましょう。
具体的には、裁判所(弁護士)基準での慰謝料の算定や、客観的な証拠に基づく過失割合の反論・立証を行うのが一般的です。
もっとも、裁判所(弁護士)基準での慰謝料の算定を行うのであれば、弁護士に交渉を委任する必要があり、被害者自らが裁判所(弁護士)基準による交渉を行っても保険会社は応じません。
また、自分に有利な過失割合を立証するために、どのような証拠をどうやって収集するのかを検討、実行するのは、専門知識や交通事故処理の豊富な経験がなければ困難です。
そのため、示談交渉を有利に進めるためには、交通事故処理の豊富な経験を有する弁護士に相談の上、交渉を依頼することが重要になります。
示談交渉を進める際の注意点については、以下の記事でも解説していますので、併せてご参照ください。
(6)示談書の取り交わし・示談金の受け取り
示談交渉で話がまとまれば、示談書を取り交わします。
その後、示談書で指定した口座に示談内容に沿った金額が振り込まれますので、正しい金額が入金されているかを確認しましょう。
なお、示談書の内容や受け取った際に確認すべきポイントについては、以下の記事をご参照ください。
4.示談を弁護士に依頼するメリット

示談を弁護士に依頼することで、さまざまなメリットがあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 示談交渉を一任できる
- 受け取れる賠償金の増額が期待できる
- 早期に賠償金を受け取れる可能性が高まる
順にご説明します。
なお、示談交渉を進める際の注意点やポイントについては、以下の記事も参考になるので、ぜひご確認ください。
(1)示談交渉を一任できる
弁護士に対応を依頼することで、示談交渉を一任でき、余計なストレスがかからない点が大きなメリットです。
示談交渉を被害者本人が行う場合、交渉に必要な根拠資料等を自らが用意しなければならず、相手保険会社と粘り強く交渉をすることが求められます。
また、加害者側は示談金を減額するために、被害者の非を主張してくることも考えられますので、被害者は、通常よりも強い精神的なストレスを受ける可能性があります。
弁護士に示談交渉を任せれば、交渉に関するストレスから解放され、日々の生活を安心して送ることができます。
(2)受け取れる賠償金の増額が期待できる
弁護士に依頼することで、裁判所(弁護士)基準で算定した賠償金を請求できるようになるため、受け取る賠償金の増額が期待できます。
保険会社が提案する賠償金は、裁判所(弁護士)基準で算定した賠償金に比べるとかなり低いことが多くあります。
怪我や後遺傷害の程度によりますが、100万円以上の差が生じることもありますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
(3)早期に賠償金を受け取れる可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、早期に示談が成立し、賠償金を早く受け取れる可能性が高まります。
交通事故処理についての豊富な専門知識や経験がなければ、客観的な資料をもとに的確な主張をすることが難しく、加害者側を納得させられない可能性があります。
交通事故の事件処理を多く行っている弁護士であれば、過去の事例にもとづいて客観的な証拠をもとに的確な主張をすることができ、被害者にとって有利になるように交渉を進めることが可能です。
そのため、スピーディに示談交渉を進め、早期に示談金を受け取ることにもつながります。
まとめ
示談交渉では、事故の過失割合や慰謝料について話し合いを行うのが一般的です。
交通事故の被害に遭われた方は、まずは弁護士に相談して、どのように対応すべきかアドバイスを受けましょう。
また、弁護士に示談交渉を依頼すれば、慰謝料の増額や示談交渉の負担軽減につながります。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、加害者側との示談交渉を控えている方はお気軽にご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事
















































