個人再生を行うための要件とは?個人再生ができない場合やほかの方法についても解説

「個人再生を行うための要件にはどんなものがある?」
「手続の流れや注意点などについて知りたい」
「個人再生を行うことができないケースにはどんなものがある?」
借金の返済が滞り、債務整理を行うことを検討されている方の中には、個人再生についてこのような疑問をお持ちの方もいると思います。
個人再生は、裁判所を介して進行する手続であり、裁判所への申立てが必要となる手続です。
そのため、個人再生を行うためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
本記事では、個人再生を行うための要件や個人再生ができないケースなどについて解説します。
また、個人再生を行うことができない場合にとりうる手続についても合わせて解説しています。
これから個人再生を行うことを検討されている方の参考となれば幸いです。
なお、個人再生の概要や手続のメリット・デメリットなどの詳細については、以下の記事も合わせてご覧ください。
1.個人再生を行うための要件

個人再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の総額に応じて減額された金額を再生計画に従って返済する手続です。
個人再生には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つがあります。
主に使われているのは小規模個人再生手続ですので、本記事では、小規模個人再生を中心にご説明します。
いずれの個人再生手続も裁判所を介して手続が進行するため、個人再生を行うためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
裁判所に申立てを行うための要件は、以下のとおりです。
まず、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続に共通する要件として、以下のものがあります。
- 支払不能の生ずるおそれがあること
- 継続的に安定した収入を得る見込みがあること
- 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を超えないこと
そして、給与所得者等個人再生のみの要件として、以下のものが挙げられます。
- 過去7年間に免責または再生計画の認可決定・ハードシップ免責を受けていないこと
- 収入の変動幅が小さいこと
借金の減額を受けるためには、手続を進め、裁判所から再生計画案の認可を受けることが必要です。
再生計画案の認可を受けるための要件については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(1)支払不能の生ずるおそれがあること
個人再生を行うためには、債務者に支払不能の生ずるおそれがあることが必要です。
支払不能であるかどうかは、債務を3年程度で返済することができるかどうかが目安となります。
そのため、一時的に支払が滞っているだけであったり家計のやりくりなどによって借金を返済することができたりという場合には、支払不能の生ずるおそれがあるとはいえません。
このような場合には、要件を満たさないため、個人再生を申し立てても手続を進めることができません。
(2)継続的に安定した収入を得る見込みがあること
個人再生を裁判所に申し立てたあと、認可を受けるために作成する再生計画案においては、減額された債務を原則3年(特別の事情があれば5年)で分割して返済を行うことを定める必要があります。
そして、再生計画案の認可を受けるためには、その計画どおりに返済ができる見通しが立つ必要があります。
そのため、現在および将来に安定した収入が見込めない場合には再生計画案の認可を受けられなくなり、それ以上手続を行うことができないことになります。
なお、給与所得者のような収入が安定している人はもちろん、アルバイトやパート、個人事業主であっても、収入や生活状況によっては再生計画案の認可を受けることは可能です。
もっとも、継続的に安定した収入を得る見込みがあることを裁判所に対して具体的に証明することが必要となります。
例えば、アルバイトやパートで、短期間のアルバイトなどを転々としているような場合には認可を受けられない可能性があるため、注意が必要です。
また、個人事業主の場合は、過去の確定申告の書類などに基づいて証明する必要があるため、確定申告を怠らないようにすることも必要です。
さらに、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続では、収入に関する要件が異なります。
2つの手続の概要や収入要件については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(3)住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を超えないこと
住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えるような大規模なものについては、個人再生の手続を行うことはできません。
個人再生は、企業の債務整理手続の1つである民事再生手続を簡略化し、個人が利用できるようにした制度です。
そのため、借金総額が5000万円を超える場合には個人再生を行うことはできません。
したがって、個人再生手続の申立てを検討する際には、借金総額がいくらなのかを確認しましょう。
借金総額が5000万円を超える場合には、自己破産などのほかの手続を行うことを検討することになります。
(4)過去7年間に免責または給与所得者等再生計画の認可決定・ハードシップ免責を受けていないこと
給与所得者等再生を行う場合には、過去に破産して免責許可決定を受けていないなどの要件も必要となります。
小規模個人再生では、債権者の意見を聞き、過半数が反対した場合には再生手続をすることができません。
それに対して、給与所得者等再生では、債権者の意見を聞くことなく再生手続をすることができます。
過去に免責等を受けた人が短期間に再度給与所得者等再生を受けられるとすると、債務者のリスク管理が甘くなってしまうおそれがあるため、それを防ぐために設けられた要件です。
したがって、過去7年以内にこれらの事情がある場合には、任意整理などほかの手続を選択する必要があります。
(5)収入の変動幅が小さいこと
給与所得者等個人再生の場合には、収入の変動幅が小さいことも必要となります。
(4)のとおり、給与所得者等再生は債権者の意見を聞くことなく手続が進みます。
そのため、再生計画案どおりに返済ができるかどうかは、債権者の同意に代わる要件を設けてチェックする必要があります。
収入の変動幅が小さければ返済を継続できる可能性が高いといえますから、それを要件にしている、というわけです。
債務者の収入状況や経済情勢などを総合的に考慮して判断されるものなので、明確な基準があるわけではありませんが、変動幅が20%未満であれば、変動幅が小さいと判断されると考えられます。
2.個人再生の手続の流れ

個人再生は、裁判所への申立てを行うことが必要です。
具体的には、以下の流れで手続を行います。
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知の送付
- 個人再生申立ての準備
- 個人再生の申立て・手続開始決定
- 履行テスト
- 再生計画案の作成・提出
- 再生計画案の認可決定・返済の開始
個人再生は裁判所とのやりとりを行う必要があるため、手続全体に時間がかかる傾向にあります。
手続の流れや手続に要する大まかな期間などについては、以下の記事も参考になります。
(1)弁護士に相談・依頼
個人再生を行う場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
借金問題については相談料を無料としている法律事務所も多いため、弁護士から専門的なアドバイスを無料で受けることができる点が大きなメリットといえます。
個人再生は裁判所を通して行う手続であるため、裁判所へ提出する書類や資料が多数あり、その中には、自分で作成する必要があるものもあります。
しかし、書類にどのようなことを記載する必要があるのかやどのような資料が必要となるかについては、専門知識や実務経験がなければ判断が難しい場合がほとんどです。
弁護士に相談・依頼することで、書類作成や資料収集についてサポートを受けることができます。
個人再生を行うにあたって必要な書類の詳細については、以下の記事もご参照ください。
(2)受任通知の送付
弁護士に手続を依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。
債権者は受任通知を受け取った後には、債務者に対して直接督促や取立てを行うことができなくなるため、この時点で返済をストップさせることができます。
これによって、今まで返済にあてていた金額を積み立てることで、裁判所費用や弁護士費用を捻出することが可能です。
同時に、債権者から債権額や取引履歴などの情報を提供してもらい、正確な借金総額を把握します。
なお、個人再生を行う際に必要な費用項目については、以下の記事も参考になります。
(3)個人再生申立ての準備
弁護士は、個人再生申立ての準備として、財産状況の確認や申立書類の作成をします。
個人再生は、借金を減額できることがメリットですが、個人再生によって減額できる借金額は、自己破産を選択した場合の債権者への配当額を下回ってはならないという「清算価値保障原則」があります。
自己破産をした場合、破産者の財産を換価して、債権者へ配当することになります。
したがって、清算価値を把握するために、現金や預貯金はもちろん、不動産や自動車の価値、退職金見込み額などを調査する必要があります。
また、それと並行して、弁護士は申立てに必要な書類(申立書、債権者一覧表、財産目録など)を作成することになります。
その際、作成に必要な資料を収集するなど、債務者自身も手続に協力する必要があります。
(4)個人再生の申立て・手続開始決定
裁判所に対して書類や資料を提出することによって申立てを行います。
書類や資料に基づいて裁判所が審査し、申立要件を満たしていると判断されると、再生手続開始決定が出されます。
なお、裁判所の判断によって、個人再生委員が選任されるケースもあります。
個人再生委員は、財産状況や収入などをチェックし、適正な再生計画案を作成するためのアドバイスを行う役割を担います。
個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員との面談があり、個人再生を申し立てるに至った経緯や財産状況について説明を求められます。
どのような運用となっているかは裁判所によって異なるため、あらかじめ弁護士に確認しておくことが重要です。
弁護士に手続を依頼することで、個人再生委員が選任された場合でも、アドバイスやサポートを受けながら落ち着いて対応を進めることができます。
(5)履行テスト
申立てがなされ、手続開始決定が出された後、6か月にわたって履行テストが行われます。
履行テストは、再生計画案で予定されている金額を毎月指定された口座に振り込むことによって実施されます。
これは、再生計画案が認可された後に継続的に返済を行っていくことができるかどうかを確かめるために行われる手続です。
履行テストにおいて予定どおりの支払ができないと、返済能力がないと判断され、再生計画案の認可がされない可能性があります。
なお、個人再生委員が選任される運用を行っている裁判所では、履行テストによって支払われた金額の一部が個人再生委員の報酬にあてられます。
個人再生委員の報酬にあてられた額を差し引いた残金については、履行テストが終了した時点で返金されます。
(6)再生計画案の作成・提出
再生計画案は、減額された借金をどのように返済していくかについて記載した書類です。
再生計画案の提出には、期限が設定されており、期限を過ぎると個人再生の手続が強制的に終了とされてしまいますので、再生計画案は必ず期限内に提出しなければなりません。
個人再生で借金の減額が認められるためには、再生計画案を裁判所に認可してもらう必要があります。
再生計画案が認可されるためには、借金総額に応じて決められている最低弁済額を満たしているかどうかも重要となります。
最低弁済額の詳細や注意点などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
(7)再生計画案の認可決定・返済の開始
再生計画案が認可された後は、再生計画の内容に従って返済が開始されます。
通常、再生計画案の認可決定が出された翌月から返済がスタートする場合が多いです。
返済期間は原則3年ですが、債務総額や返済能力によっては5年とすることを認めてもらえるケースもあります。
支払を行う際には、基本的には各債権者の口座に直接振り込むことになるため、毎月の払い忘れにも注意をしましょう。
3.個人再生ができない・失敗してしまう主なケース
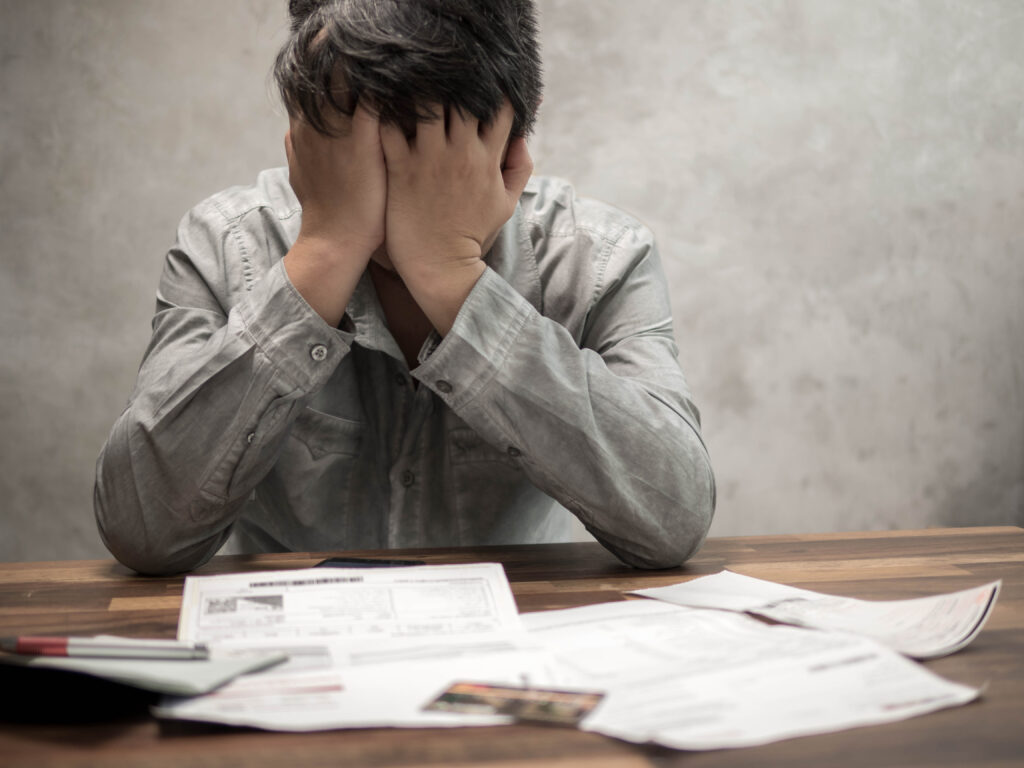
先ほども述べたように、個人再生を行うためには裁判所に申し立てることが必要です。
申立て時点で上記のような要件を満たしていない場合には、個人再生を行うことができないため、注意が必要です。
また、それ以外にも以下のようなケースに該当すると、個人再生を行うことができなくなったり、失敗してしまったりします。
- 一部の債権者のみに優先的に返済を行った
- 手続中に新たな借入れを行った
- 高額な財産を所有している
- 手続の費用を納付できない
- 必要な書類や資料を期日までに提出できない
- 履行テストを怠る
個人再生を行うことを検討されている方は、ご自身がこれらに該当していないかを確認しておきましょう。
なお、以下の記事も合わせてご覧ください。
(1)一部の債権者のみに優先的に返済を行った
特定の債権者のみに優先的に返済を行うことを偏頗弁済といいます。
個人再生においては、すべての債権者を平等に扱わなければならない「債権者平等の原則」を遵守することが必要です。
特定の債権者のみに返済を行うことは、この「債権者平等の原則」に反するため、禁止されているのです。
偏頗弁済を行ってしまうと、偏頗弁済を行った金額が最低弁済額に上乗せされてしまい、個人再生を行うメリットがなくなってしまう可能性があります。
また、偏頗弁済の程度がはなはだしい場合は、裁判所に知られた時点で個人再生の手続をそれ以上進めてもらえなくなる可能性もあります。
家族や友人からの借入れがある場合、どうしても返済したいと思うかもしれませんが、個人再生を行う上で偏頗弁済をしてもよいことはないため、しないようにしましょう。
どのような行為が偏頗弁済にあたるのかについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(2)手続中に新たな借入れを行った
個人再生の手続開始決定までに新たな借入れを行ってしまうと、個人再生手続を進められなくなる可能性があります。
支払不能のおそれがある場合には、その時点での債権者に不利益を及ぼさないよう、自己破産や個人再生の手続をとるのが望ましいといえます。
特に、弁護士に個人再生を依頼したあとは、個人再生手続において、債権者が損をしないように行動することが求められます。
そのような状況で新たな借入れをすると、その分、再生計画案に定めるべき返済額が増えてしまい、元の債権者が返済を受けられなくなるリスクが増すことになります。
このような行為は慎むべきであるため、個人再生の手続の中で不利に扱われる可能性があります。
また、再生計画案の認可決定を受けて計画返済中に借入れを行ったために、返済が滞ってしまうと、債権者の申立てにより、再生計画が取り消されてしまうリスクもあります。
個人再生中に借入れを行うリスクや資金繰りに困った際の対処法については、以下の記事もご参照ください。
(3)高額な財産を所有している
先ほど説明したとおり、清算価値保障原則があるため、自分の所有している財産の価値によっては、借金を減額することができず、個人再生をするメリットがなくなる可能性があります。
具体的には、住宅などの不動産や車・バイク、預貯金や退職金などが対象となり、合計金額が民事再生法で定められた最低弁済額を上回る場合には、財産の合計金額が最低弁済額となります。
最低弁済額は以下のとおりです。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円~1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
そのため、債務者が高額な財産を所有している場合には最低弁済額も高額になり、個人再生を行うメリットが損なわれる可能性があるのです。
清算価値保障原則の概要や具体的な算定方法については、以下の記事が参考になります。
(4)手続の費用を納付できない
個人再生を行うためには、裁判所に申立て手数料、予納郵券、官報広告費などの費用として2~3万円を支払う必要があります。
裁判所への費用は申立ての時点で納付する必要があり、申立てまでに必要な費用を準備できない場合には個人再生の手続を行うことができなくなってしまうため、注意が必要です。
なお、個人再生手続を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用も必要になります。
一方、弁護士に依頼せずに申立てを行った場合には、ほとんどの裁判所で再生委員を選任する扱いになっているため、再生委員の報酬も必要になりますが、こちらは前述のとおり、履行テストによる積立てができるケースもあります。
もっとも、弁護士に手続を依頼すると、債権者に受任通知が送付され、一時的に返済がストップします。
その間に返済にあてていた金額から裁判所費用や弁護士費用を捻出しましょう。
個人再生の費用が捻出できない場合の対処法については、以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
(5)再生計画案を期日までに提出できない
個人再生を行うためには、再生計画案を期日までに作成・提出する必要があります。
再生計画案を期日までに提出できない場合には、その時点で手続が廃止(終了)となってしまうため、注意が必要です。
特にご自身で手続を行ってしまうと、必要な書類の作成や資料の収集に時間がかかり、提出期日を徒過してしまう可能性が高まります。
弁護士に相談の上、手続を依頼することで、書類作成を弁護士に任せることができ、資料収集についても的確なアドバイスやサポートを受けることが可能です。
(6)履行テストを怠る
先ほども述べたように、履行テストは、債務者に再生計画案に基づく返済能力があるかどうかを確認するための手続です。
履行テストの支払を1回でも怠ってしまうと、返済能力がないと評価され、手続が廃止(終了)となってしまいます。
そのため、履行テストでは、期限に遅れることなく支払い続けることが最も重要です。
4.個人再生ができない場合の対処法

上記のような理由で個人再生を行うことができない場合には、ほかの債務整理の手続を行うことを検討することになります。
具体的には、以下の2つが考えられます。
- 任意整理
- 自己破産
どのような手続を行うのが適しているのかは、収入や財産状況によっても異なります。
そのため、まずは弁護士に相談し、どの手続を行うことが自分に適しているのかについてアドバイスを受けることが大切です。
(1)任意整理
任意整理は、債権者と直接交渉を行い、将来利息のカットや返済スケジュールの再設定などによって月々の返済負担を軽減し、借金の完済を目指す手続です。
住宅や車などの高額な財産を所有している場合には、個人再生における最低弁済額が高額になり、借金の減額ができない可能性があるため、そのような場合には任意整理を行うことも検討しましょう。
もっとも、借金総額が大きく、将来発生する利息分をカットしても返済を行うことが困難である場合には任意整理を行うことは向いていないと言えます。
そのような場合には、次に述べる自己破産を行うことを検討することになります。
なお、任意整理のメリットやデメリット、手続の注意点などについては以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(2)自己破産
自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらう手続です。
借金総額が5000万円を超えている場合や安定した収入が見込めない場合には、自己破産を行うことを検討することになります。
もっとも、一定額以上の財産を所有している場合には、換価処分が行われ、債権者に配当が行われてしまいます。
また、破産手続中は就くことができる職業に制限があったり、裁判所の許可を得なければ転居や出張ができないなどのデメリットもあります。
自己破産を行うことによる影響などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
まとめ
本記事では、個人再生を行うための要件や個人再生を行うことができない主なケースなどについて解説しました。
個人再生は裁判所を介して手続が進むため、手続を申し立てるための要件や申し立てた後にも注意点があります。
専門知識や実務経験がなければ不備なく進めていくことは難しいため、個人再生を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、借金問題や個人再生などの債務整理の手続に数多く対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、個人再生を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事

































