自己破産を弁護士に依頼するメリットは?自分で行うリスクも解説

「自己破産の手続について弁護士に相談・依頼するメリットとは?」
「自分で自己破産の手続を行うことはできる?」
「自己破産の手続の流れや注意点などについて知りたい」
借金の返済を滞納してしまい、支払いの目途が立たない方の中には、債務整理を行うことを検討されている方もいると思います。
また、債務整理の中でも、自己破産についてこのような疑問や不安をお持ちの方もいるでしょう。
自己破産は裁判所に申立てを行い、借金の返済が困難であることを認めてもらい、裁判所に借金の返済義務を免除してもらう手続です。
また、自己破産の手続は法律の定めに従って厳格に進められるため、提出書類や手続の進行に際して不備があれば、借金の返済義務の免除を受けられない可能性があります。
本記事では、自己破産の手続を弁護士に相談・依頼するメリットや債務者ご自身で自己破産を行うリスクなどについて解説します。
自己破産を行うことを検討されており、弁護士へ相談するかどうかについて悩まれている方の参考となれば幸いです。
1.自己破産について弁護士に相談・依頼するメリット

自己破産は、裁判所に借金の返済が困難であることを認めてもらい、裁判所から借金の返済義務の免除(免責許可決定)を受ける手続です。
なお、債務者が一定以上の財産を所有している場合には、裁判所が選任する破産管財人によってその財産の換価処分が行われ、換価された金銭が債権者に配当されます。
また、不備が無いように申立書類を作成し、必要書類を収集してから、裁判所への申立てが必要となるため、専門知識や実務経験が必要です。
そのため、自己破産を行うことを検討されている方は、まずは自己破産の手続きに経験を有する弁護士に相談や依頼をするのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 無料で専門的なアドバイスを受けることができる
- 債権者からの督促や取立てがストップする
- 書類作成や資料収集についてサポートを受けられる
- 予納金を低く抑えて手続を行える可能性がある
- 債権者や裁判所との対応を任せられる
- 免責に向けたアドバイスやサポートを受けられる
なお、以下の記事も参考になります。
(1)無料で専門的なアドバイスを受けることができる
自己破産をはじめとする債務整理の手続に関しては、相談料を無料としている法律事務所が多いです。
そのため、自己破産を行うか判断に迷う場合には、弁護士に相談することで、無料で専門的なアドバイスを受けることができます。
例えば、自己破産を行うと、債務者に一定以上の財産がある場合には、その財産が手続の中で換価処分が行われ、債権者に配当されてしまいます。
そのため、住宅や車などの高額な財産を所有している場合には、これらを手放さなければならない可能性が高いことに注意が必要です。
弁護士に相談することで、収入や生活状況などを踏まえて、自己破産を行うべきかどうかだけでなく、ほかに最適な解決方法がないかについても説明を受けることができます。
(2)債権者からの督促や取立てがストップする
弁護士に自己破産の手続を依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知を受け取った債権者は、それ以降に債務者に対して直接督促や取立てを行うことができなくなります。
そのため、受任通知が送付されると、借金の返済が一時的にストップするのです。
債権者からの連絡がなくなるため、精神的にも安心ができ、弁護士のサポートを受けながら手続に向けて準備を進めることができることも大きなメリットの1つでしょう。
(3)書類作成や資料収集についてサポートを受けられる
すでに述べたように、自己破産を行うためには、裁判所に申立てを行うことが必要です。
申立ての際には申立書面のほかにも添付資料などを提出する必要があります。
必要となる書類や資料は多岐にわたるため、専門知識や実務経験がなければこれらの作成や収集をスムーズに進めることは困難です。
弁護士に手続を依頼することで、申立書面の作成を任せたり、どのような書類や資料が必要となるのかについて説明を受けることができます。
慣れない書類作成や資料収集についてもアドバイスやサポートを受けることができるため、申立てまでスムーズに進めることが可能です。
(4)予納金を低く抑えて手続を行える可能性がある
自己破産を行うためには、裁判所に予納金という費用を納付する必要があります。
自己破産の手続きは、債務者の財産状況などによって、同時廃止事件と管財事件の二種類に振り分けられるのですが、債務者に一定以上の財産がある場合や財産の有無が申立ての時点で明らかではない場合には、管財事件に振り分けられます。
この管財事件では、債務者の財産を換価して金銭を債権者に配当することが前提とされるため、手続が同時廃止事件と比べて複雑になり、裁判所に納める予納金も高額化する傾向にあることに注意が必要です。
なお、管財事件の中には比較的定型的な処理が行われる少額管財事件の運用を行っている裁判所もあります。
少額管財事件では裁判所に納める予納金の相場が20万円程度になるケースが多く、通常の管財事件と比較すると低額になります。
もっとも、少額管財事件に振り分けられるための条件としては、弁護士に申立手続を依頼していることが挙げられます。
そのため、弁護士に手続を依頼し、少額管財事件となれば、予納金を低く抑えられる可能性があるのです。
なお、予納金の費用項目や相場については、以下の記事もご覧ください。
(5)債権者や裁判所との対応を任せられる
自己破産の手続では、裁判所への出廷や債権者からの連絡に対応が必要となる場面もあります。
具体的には、自己破産へ至った経緯などについて裁判所や債権者に説明を行わなければならないケースがあります。
どのような対応を行えばよいかは自己破産手続の知識や経験がなければ戸惑ってしまうことも多いです。
そのため、弁護士に手続を依頼することで、これらの対応を任せることができるほか、ご自身で対応を行う必要がある場合にあらかじめアドバイスやサポートを受けることができます。
なお、裁判所へ出廷するタイミングや内容については、以下の記事もご覧ください。
(6)免責に向けたアドバイスやサポートを受けられる
借金の返済義務を免除してもらうためには、裁判所から免責許可決定を受けることが必要です。
自己破産の申立を裁判所に行ったとしても、最終的に免責許可決定を受けることができなければ、返済義務がなくならず、意味が無い結果になってしまいます。
具体的には、破産法に「免責不許可事由」として定められている事由に該当する場合には、裁判所から免責許可決定を受けられない可能性があるため、注意が必要です。
以下のような事情が免責不許可事由に該当します。
- 財産の隠匿・処分を行った
- 特定の債権者のみに返済を行った(偏頗弁済)
- 換金行為を行った
- 借金の主な原因が浪費やギャンブルなどの行為だった
- 申立書類や添付資料を偽造した など
もっとも、これらの事情に該当する場合であっても、裁判所が裁量で免責を認める「裁量免責」の制度もあります。
実際には免責不許可事由があっても、この裁量免責の制度によって免責になっているケースは多いです。
弁護士に手続を依頼することで、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、裁量免責を受けるためのアドバイスやサポートを受けることが可能です。
免責不許可事由の詳細や具体例については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
2.自己破産の手続の流れ
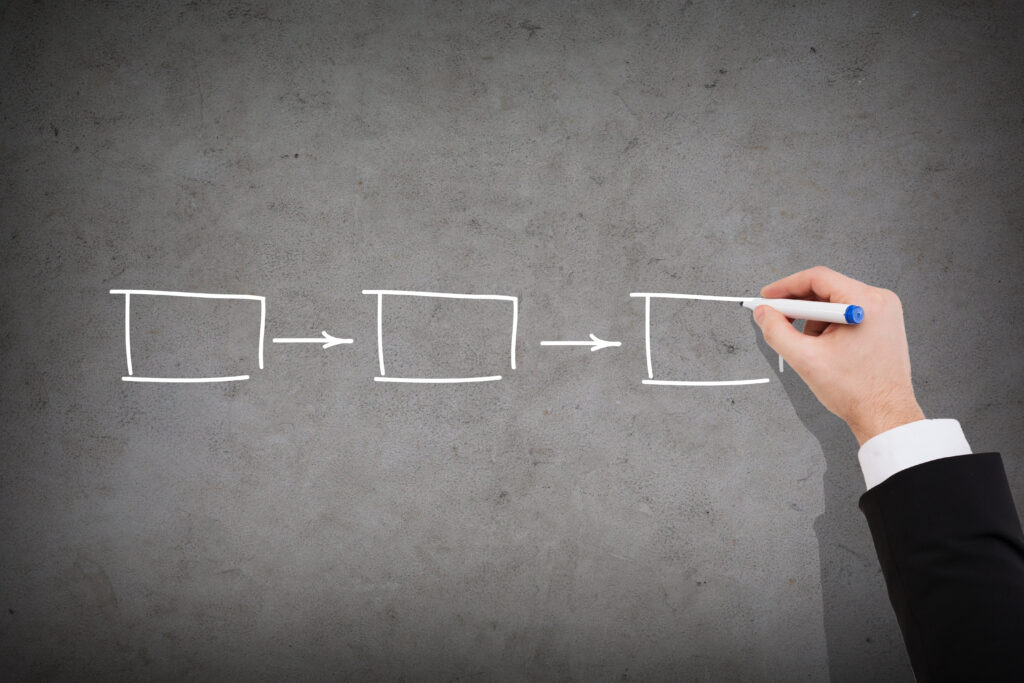
自己破産の手続は、法律や実務上の便宜から進行の流れが概ね定まっています。
具体的には、以下の手順で進められます。
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知の送付
- 申立書類の作成・添付資料の収集
- 破産手続の申立て
- 破産手続開始決定
- 破産管財人の選任
- 財産調査・換価処分
- 債権者集会
- 免責許可決定
なお、自己破産の手続の流れや概要については以下の記事も参考になります。
(1)弁護士に相談・依頼
まずは弁護士に相談することが大切です。
先ほども述べたように、借金問題については相談料を無料としている法律事務所が多いため、専門家である弁護士から無料でアドバイスを受けることができるのが大きなメリットと言えます。
ご自身の収入や生活状況、支出などから、自己破産を含めて債務整理の各手続きの中で最適な解決方法の提案を受けることができます。
なお、自己破産を行うのに適している条件については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(2)受任通知の送付
弁護士に手続を依頼すると、弁護士から債権者に受任通知が送付されます。
貸金業者などの債権者はこの受任通知を受け取った後、債務者に対して直接督促や取立てを行うことが禁止されるため(貸金業法21条1項9号)、毎月の返済がここでストップします。
なお、自己破産を行う際には、裁判所に納める費用が必要となるほか、手続を依頼する弁護士の弁護士費用も必要となります。
弁護士が受任通知を出して毎月の返済がストップしている間、必要な費用を一括又は分割で準備しましょう。
(3)申立書類の作成・添付資料の収集
弁護士に任せたり、弁護士のサポートを受けながら提出書類の作成や添付資料の収集を行います。
裁判所に提出する書類としては、自己破産の申立書、家計簿、預金通帳の写しなどがあります。
また、住宅や車を所有している場合には、不動産登記事項証明書や車検証のコピーなども必要になります。
どのような書類や資料が必要となるかはそれぞれの方の財産状況によっても異なるため、弁護士と相談しながら進めることが重要です。
申立てに必要な書類や入手方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
(4)破産手続の申立て
必要書類・資料を裁判所に提出して裁判所に自己破産の申立てを行います。
また、申立てと合わせて裁判所に予納金の納付を行う必要があります。
先ほども述べたように、予納金を納付できない場合には手続を進めることができなくなってしまうため、申立ての時点までに用意しておくことが重要です。
予納金を払えない場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
(5)破産手続開始決定
裁判所によって申立書面の審査が行われ、不備が無ければ手続開始決定が出されます。
この際に、債務者の財産状況などから、同時廃止事件か管財事件のどちらかの手続に振り分けられます。
同時廃止事件の場合には、開始決定と同時に手続が廃止(終了)となります。
なお、同時廃止事件となる条件や手続の特徴などについては、以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。
管財事件に振り分けられれば、免責不許可事由や債務者の財産の調査、換価処分などが行われます。
管財事件に振り分けられる条件や手続の注意点などについては、以下の記事もご参照ください。
(6)破産管財人の選任
管財事件に振り分けられると、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人は、弁護士の中から選任され、債務者の免責不許可事由の調査、財産を換価処分、債権者への配当を行う役割を担います。
破産管財人が選任されると、債務者との間で面談が行われることが通常です。
面談では、現在や過去の財産や入出金の内容、免責不許可事由に関する事情などについて聞き取り調査が行われます。
債務者は、破産管財人の調査に協力する義務を負うため、調査を拒否したり虚偽の説明を行ったりしないようにする必要があります。
破産管財人の概要や具体的な役割などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(7)財産調査・換価処分
債務者の生活に必要な一定の財産(自由財産)を除いた他の財産については、破産管財人が管理・処分を行います。
破産管財人は、財産を調査し、適正な価格で売却・処分を行うことで、債権者への配当原資を維持・増加させる責務を負っています。
そのため、不当に債務者が流出させてしまった財産を回復させ、債権者への配当原資を維持・増加させる否認権という権利も有しているのです。
自由財産の具体例については、以下の記事も参考になります。
また、否認権の概要や行使されるケースなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(8)債権者集会
財産の換価処分が完了した段階で、破産管財人が調査や換価処分の結果を債権者に報告する債権者集会が開かれます。
債権者集会には債務者も出席する義務があり、債権者から質疑があった場合には、回答しなければならないことがあるため、注意が必要です。
もっとも、実際には債権者が出席せずに債権者集会を終えることが多いです。
また、債権者が出席しているケースでも、弁護士に手続を依頼している場合には、債権者対応を任せたり、ご自身で対応する際に事前にアドバイスやサポートを受けることができます。
なお、債権者集会に続いて免責を認めてよいかを判断する免責審尋が一緒に行われます。
(9)免責許可決定
免責審尋の内容に基づいて、裁判所から免責許可決定が下されます。
具体的には、以下のいずれかの場合に免責許可決定を受けることが可能です。
- 免責不許可事由に該当する事由がない場合
- 免責不許可事由に該当するが、裁判所が免責を認めてよいと判断した場合
そのため、免責不許可事由に該当するような事情があったとしても、裁判所の裁量によって免責を受けられる可能性があります。
具体的には、債務者が真摯に反省し、更生の余地があると裁判所に判断してもらうことが重要です。
弁護士のサポートやアドバイスを受けながら、裁量免責を受けるための対策を進めましょう。
3.債務者が自分で自己破産の手続を行うリスク

自己破産の手続は、弁護士に依頼することなく債務者ご自身で行うことも可能です。
債務者が自ら手続を行うことができれば弁護士費用は不要となります。
もっとも、上記のように自己破産の手続は複雑であるため、不備が無いようにスムーズに進めていくためには、専門知識や実務経験が必要となります。
また、債務者がご自身で手続を進めてしまうと、以下のようなリスクがあることに注意が必要です。
- 債権者からの督促や取立てがストップしない
- 書類作成や資料収集をすべて自分で行わなければならない
- 予納金が高額になる可能性がある
- 免責を受けるのが難しくなる可能性がある
順にご説明します。
(1)債権者からの督促や取立てがストップしない
債務者が自らで自己破産の手続を進めると、弁護士の受任通知が送付されません。
そのため、債権者からの督促や取立てを止めることができないことに注意が必要です。
特に債権者からの連絡が続く中で自己破産の申立てへ向けた準備を行っていくことには心理的な負担も小さくないでしょう。
(2)書類作成や資料収集をすべて自分で行わなければならない
先ほども述べたように、自己破産の申立てを行う際には、様々な書類を作成し、添付資料を収集する必要があります。
ご自身で手続を進める際には、書類の作成や資料の収集もすべてご自身で進めることになります。
特に所有する財産などによって、準備すべき添付資料は多岐にわたります。
また、申立書類に不備などがあれば、裁判所から開始決定がなかなか出ない可能性があります。
どのような点に注意しながら書類作成や資料収集を行えばよいのかなど弁護士に相談や依頼をすることが望ましいでしょう。
(3)予納金が高額になる可能性がある
ご自身で申立てを行うと、手続は原則として管財事件に振り分けられます。
これは、収入や財産に関する事項や免責不許可事由の有無などについて、管財人による詳細な調査が必要となるためです。
そのため、ご自身で自己破産の手続を行ってしまうと、予納金が高額になってしまう可能性が高いです。
弁護士に相談し、手続を依頼することで、予納金の相場を低く抑えることができる少額管財事件に振り分けられる可能性が高まります。
もっとも、全ての裁判所が少額管財事件の制度を設けているわけではないため、あらかじめ弁護士に相談・確認しましょう。
(4)免責を受けるのが難しくなる可能性がある
借金の返済義務を裁判所に免除してもらうためには、免責許可決定を受ける必要があります。
免責不許可事由に該当する事情があれば、返済義務を免除してもらえない可能性があることに注意が必要です。
もっとも、免責不許可事由があったとしても、裁判所の裁量で免責が認められる裁量免責の制度があります。
どのような対応を行えば裁量免責を受けることができるのか知識、経験がなければ分からないことも多いため、弁護士に相談して手続を依頼することによって裁量免責を受けるための対策をすることが望ましいでしょう。
まとめ
本記事では、自己破産を弁護士に相談・依頼するメリットやご自身で手続を行うリスクなどについて解説しました。
自己破産は裁判所に申立をして進める透明性の高い手続であるため、様々な注意点などがあり、スムーズに進めていくためには専門知識や実務経験が必要不可欠です。
手続を理解しないままでご自身で進めてしまうと、免責許可決定を受けられない可能性もあるため、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、借金問題や自己破産などの債務整理の手続に数多く対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、自己破産を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事































