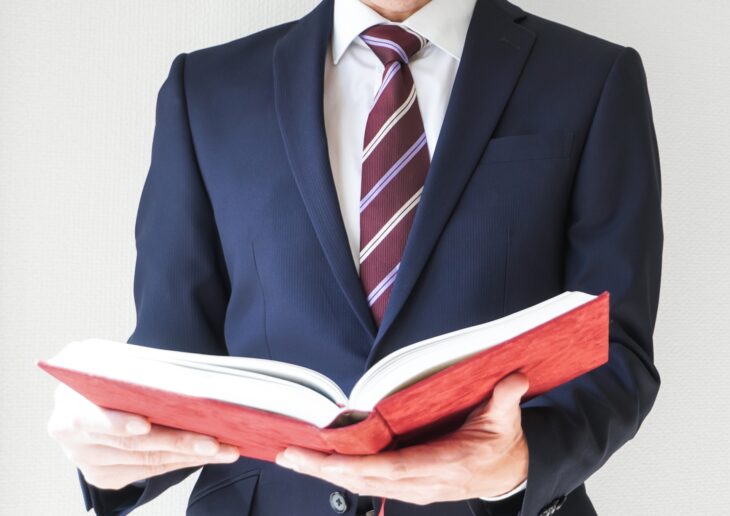管財事件の流れとは?目安となる期間や費用、破産手続の注意点も解説

「破産の管財事件とはどのような手続の流れなのか」
「破産手続が終了するまでの目安の期間や裁判所費用の相場は?」
「管財事件となった場合に注意すべき点について知っておきたい」
自己破産を行うことを検討されている方の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
自己破産の手続は、裁判所に申し立てた後、裁判所によって管財事件か同時廃止事件のどちらかの手続に振り分けられます。
管財事件は破産手続の基本となる手続であり、債務者の財産について換価処分を行い、債権者に対して配当を行うことが予定されている手続です。
そのため、手続が複雑になり、手続の進行について様々な注意点があります。
本記事では、自己破産手続の中でも、管財事件の流れや目安となる期間などについて解説します。
また、管財事件として振り分けられた場合に押さえておくべき注意点についても合わせて解説しています。
なお、自己破産手続のうち、同時廃止事件については、以下の記事で解説していますので、合わせてご参照ください。
1.管財事件の流れ
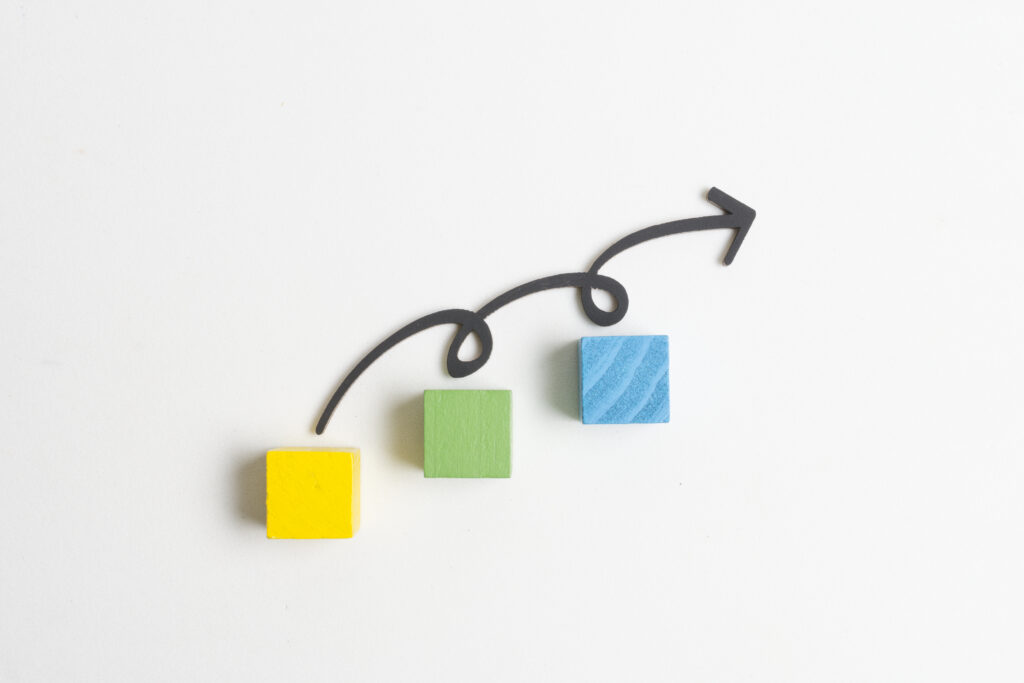
管財事件は、債務者に一定額以上の財産がある場合などに振り分けられる手続です。
手続の中で財産の換価処分と債権者への配当が予定されているため、手続が複雑になります。
具体的には、以下の流れで進行します。
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知の送付・申立準備
- 破産手続開始申立て
- 債務者審尋
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任
- 財産調査・換価処分
- 債権者集会
- 免責許可決定
なお、管財事件の概要や振り分けられる基準の詳細については、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
(1)弁護士に相談・依頼
自己破産を行うことを検討されている場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
多くの法律事務所では、自己破産をはじめとする債務整理の手続に関しては相談料を無料としています。
そのため、弁護士から無料で専門的なアドバイスやサポートを受けることが可能です。
また、自己破産は裁判所を通して行うため、手続を行うための要件を満たす必要があるほか、申立ての際に提出する書類や資料も多岐にわたります。
弁護士に相談することで、これらについても説明を受けることができ、不安や悩みを解消することができます。
また、そのまま手続を依頼することもできるため、スムーズに破産の準備を進めていくことが可能です。
なお、自己破産について弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
また、自己破産を申し立てるための要件については、以下の記事でも解説しているので、合わせてご参照ください。
(2)受任通知の送付・申立準備
弁護士に手続を依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。
債権者が受任通知を受け取ると、それ以降は債務者に対して直接督促や取立てを行うことが禁止されます。
そのため、受任通知が送付されると、一時的に督促や取立てが停止し、返済がストップするのです。
この間に自己破産の申立てを行う準備を進めることになります。
具体的には、弁護士のサポートを受けながら申立書類の作成に必要な事情を弁護士に話したり、提出が必要な資料の収集を行いましょう。
必要となる申立書類や添付資料には、以下のようなものがあります。
- 自己破産申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 不動産登記簿の謄本
- 車検証
- 給与明細
- 源泉徴収票 など
申立書類の作成については弁護士に任せることができるため、まずはアドバイスやサポートを受けながら提出が必要な資料の収集を行うことが中心です。
また、自己破産を行うためには弁護士費用や裁判所へ納付する費用が必要となることも押さえておきましょう。
弁護士費用を分割で支払っていく場合は、毎月定められた期日までにきちんと支払いをしていかないと、自己破産手続を行うことができなくなってしまうため、借金の返済がストップしている間に必要な費用の支払いをすることが大切です。
自己破産の申立てに必要な書類と添付資料については、以下の記事もご覧ください。
また、自己破産の費用を捻出するための対処法については、以下の記事も参考になります。
(3)破産手続開始申立て
申立書類と添付資料の準備ができれば、これらを裁判所に提出することによって破産手続の申立てを行います。
この際に手続に必要な裁判所費用も納付する必要があるため、申立ての時点までに必ず必要な費用を準備しておくことが大切です。
(4)債務者審尋
申立てを行った後は、裁判所から申立書類の内容について質問や面接が行われる場合があります。
手続を弁護士に依頼している場合でも、もし裁判所から呼び出しを受けた場合には必ず債務者本人が出廷して応じなければならないことに注意が必要です。
また、手続の流れにも関わるため、裁判官から聞かれたことに対しては正直に答えることが大切です。
なお、東京地裁では債務者審尋に代えて、申立ての当日か遅くとも3日以内に「即日面接」という期日が設けられます。
この期日では、裁判官と代理人弁護士との間で今後の手続の流れなどについて打ち合わせが行われます。
即日面接が行われる際には債務者の立ち合いは認められておらず、出廷する必要はないものの、この期日で管財事件か同時廃止事件の振り分けが決められます。
(5)破産手続開始決定・破産管財人の選任
申立書類や添付資料に不備がなければ、破産手続開始申立てから概ね1週間以内に破産手続開始決定が出ます。
また、債務者審尋や即日面接の結果、管財事件に振り分けられた場合には、裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産管財人は、債務者の財産を調査・管理し、適正価格で換価した上で債権者に配当を行う役割を担う人をいい、通常は弁護士の中から選任されます。
そのため、破産管財人が選任されると、この時点で債務者の財産の管理は破産管財人が引き継ぎますので注意が必要です。
破産管財人の概要や手続で果たす役割などについては、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
(6)財産調査・換価処分
破産管財人は、債務者の生活に必要な一定の範囲の財産(自由財産)を除いたあらゆる財産について調査・管理を行います。
先ほども述べたように、破産管財人は債務者の財産を適正価格で換価し、得たお金を債権者へ配当する役割を担っているためです。
さらに、破産管財人は、債権者への配当の原資を確保して、その価値を維持・増加させる責務も負っています。
そのため、債務者が不当に配当原資となる破産財団から流出させた財産がある場合には、破産管財人はこれを債務者の手元に回復させるための「否認権」という権利を有します。
否認権が行使される状況については、債務者が財産を売却・譲渡することで配当原資を減少させる行為や特定の債権者のみに返済や担保の供与を行う行為などが挙げられます。
破産管財人によって否認権が行使されると、その法律行為は効力が否定され、流出した財産が破産財団に戻ることとなるのです。
否認権の意義や行使される具体的なケースについては、以下の記事でも解説しています。
(7)債権者集会
財産調査と換価処分が終了すれば、債権者集会が開かれます。
債権者集会は、破産管財人が換価処分の状況や配当などについて債権者に報告するための期日です。
換価処分の結果、債権者に配当できるほどの財産がある場合には、配当の手続も行われます。
債権者集会には債務者本人も出席する義務があり、債権者から質疑などがあればこれに答えなければならないことを押さえておきましょう。
もっとも、債権者が実際に出席するケースはほとんどなく、10分程度で終了することも多いです。
なお、通常は債権者集会に続いて免責審尋が行われることになります。
これは、裁判官が債務者と面談を行い、免責許可決定を下してよいかの判断を行うための手続です。
免責審尋も債権者集会と同様に債務者は出席する義務を負い、裁判所や破産管財人の質問に対応する必要があります。
主に簡単な事項についての質問・確認で終わることが多いものの、聞かれたことに対しては誠実かつ正直に答えることが最も重要です。
(8)免責許可決定
免責審尋の内容を踏まえて、裁判所が以下のいずれかに該当すると判断した場合には免責許可決定が下されます。
- 免責不許可事由がない場合
- 免責不許可事由があるものの免責を与えてよいと判断した場合
免責不許可事由とは、破産法上で定められている事由のことで、これが認められてしまうと借金の返済義務を免除してもらえなくなるため、注意が必要です。
具体的には、以下のような事由が挙げられます。
- 借金の主な原因が浪費やギャンブルによること
- 特定の債権者のみに返済を行ったこと(偏頗弁済)
- 換金行為を行ったこと
- 財産の隠匿・処分を行ったこと
- 債権者一覧表に虚偽の記載を行ったこと
- 裁判所や破産管財人に対して虚偽の説明を行った・説明を拒否したこと など
もっとも、これらの事由に該当していても、債務者が真摯に反省し、更生の余地があると裁判所が判断すれば、免責を受けられる裁量免責の制度があります。
免責不許可事由があったとしても裁量免責によって免責を受けられるケースは多いため、これらの事由に該当していたとしても、諦めずに弁護士に相談し、対策を行うことが大切です。
免責不許可事由の詳細については、以下の記事もご参照ください。
裁量免責を受けるためのポイントや注意点などについては、以下の記事も参考になります。
2.管財事件となった場合に手続に要する期間の目安

上記で解説したように、管財事件では債務者の財産の換価処分と債権者への配当が予定されています。
そのため、手続に要する期間が比較的長いところに特徴があります。
なお、比較的定型的な事案処理が可能な場合に手続を簡略化させる少額管財事件の運用を行っている裁判所もあります。
通常管財事件と少額管財事件とでは、手続に要する期間の長さに違いがあることも押さえておきましょう。
(1)通常管財事件
手続きに要する期間は、通常管財事件では申立から6か月~1年程度が目安です。
なお、換価処分を行うべき財産が多岐にわたる場合や財産が高額な場合のほか、債権者の数が多いような場合には、複数回にわたって債権者集会が開かれるケースもあります。
そのため、事案によってはさらに期間を要することもあるため、注意が必要です。
(2)少額管財事件
先ほども述べたように、少額管財事件は比較的定型的な事案処理が可能なものについて運用が行われます。
通常管財事件の場合と比較すると、換価処分を行うべき財産がそれほど多くないことが一般的であり、手続きに要する期間は申立から3か月~6か月程度が目安です。
なお、少額管財事件として処理されるためには、裁判所で、破産手続を弁護士に依頼していることを要件としていることがあります。
弁護士が申立てから関与することで、弁護士が事前に内容を精査し、破産管財人の負担が軽減されて手続を迅速に進めることができるのも、手続に要する期間が短縮化される要因とされています。
少額管財事件の詳細については、以下の記事も参考になります。
3.管財事件となった場合の裁判所費用の相場

管財事件となった場合には、破産管財人が選任され、債務者が破産管財人の最低限の報酬を納付することになります。
そのため、管財事件では、申立て時に裁判所に予納金を納付しなければいけないことに注意が必要です。
以下では、通常管財事件と少額管財事件の予納金の費用相場についてご説明します。
なお、同時廃止事件を含めた予納金の相場の比較については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(1)通常管財事件
債務額や持っている資産、免責不許可事由の有無などの状況によって変動するものの、50万円以上が目安ということができます。
通常管財事件では、債務者が一定額以上の財産を所有していることが前提となるため、その調査や換価処分に時間を要する場合が多いです。
また、免責不許可事由の有無について調査を行うなどの業務が多岐にわたるため、破産管財人の報酬が高額化する傾向にあることも要因として挙げられます。
(2)少額管財事件
少額管財事件として処理されると、予納金は20万円程度が目安になります。
これは、先ほども述べたように、通常管財と比較すると手続が簡略化されているためです。
そのため、少額管財事件では通常管財事件と比較すると、費用負担を抑えて手続を行うことができます。
4.管財事件に関する注意点

冒頭で述べたように、自己破産には同時廃止事件と管財事件の2つの手続があります。
このうち、管財事件として処理がなされると、同時廃止事件と比較して、以下の点に注意が必要です。
- 予納金が高額化する
- 手続全体に要する期間が長期化する可能性がある
- 破産管財人の調査に協力する義務がある
- 手続中は転居や出張が制限される
- 手続中に就くことができない職業・資格がある
- 手続中は郵送物が破産管財人に転送される
なお、破産手続全般において注意すべき事柄については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
(1)予納金が高額化する
同時廃止事件では、換価処分や債権者への配当が予定されないため、破産管財人が選任されません。
そのため、同時廃止事件では破産管財人の報酬を債務者が負担する必要がなく、その分だけ予納金が低くなります。
これに対して、管財事件では破産管財人が選任されるため、その報酬の分が予納金に上乗せされ、予納金が高額化する傾向にあることを押さえておきましょう。
(2)手続全体に要する期間が長期化する可能性がある
同時廃止事件は破産手続開始決定と同時に手続を終了させるものであり、換価処分や配当が予定されていないものであるため、比較的短期間で手続が終了します。
もっとも、管財事件では、すでに述べているように、債務者の財産を調査し、これを換価処分し、債権者に配当を行うことが前提となっています。
そのため、債務者が所有している財産が多岐にわたったり、高額であったりする場合には、財産調査や換価処分に時間がかかり、手続が長期化する傾向にあります。
(3)破産管財人の調査に協力する義務がある
管財事件では、裁判所によって破産管財人が選任され、財産の管理・処分、債権者への配当などの一部の手続の進行に関わります。
破産管財人は裁判所の役割の一部を担っているということができるため、手続中には裁判所と同様に破産管財人にも協力する義務が生じます。
具体的には、破産管財人から財産調査への協力や追加資料の提出などを求められた場合には、債務者はこれに応じなければなりません。
なお、破産管財人の調査などに応じないことは、免責不許可事由として挙げられています。
破産管財人の調査に応じないことは、ほかの免責不許可事由と比較しても、特に免責が認められにくくなるため、注意が必要です。
そのため、裁判所への対応と同様に、破産管財人に対しても聞かれたことなどについて誠実かつ正直に答えることが何よりも重要といえます。
(4)手続中は転居や出張が制限される
管財事件として処理されると、債務者は手続中に転居や出張などの移動を伴う活動が制限されることに注意が必要です。
これは、手続中に債務者が逃亡したり財産を隠匿・処分したりして手続の進行が遅れることを防止する目的があるためです。
もっとも、裁判所の許可を得ることで、転居や出張を行うことができます。
裁判所に申請を行い、許可を得るためには転居や出張の必要性を具体的に説明することが求められます。
なお、管財事件では財産の換価処分が行われるため、これによって住宅が換価処分されたことに伴う転居などの場合には、比較的認められやすいことが多いです。
また、免責許可決定を受けて手続が終了すると、裁判所への申請や許可を得ることなく転居や出張などを行うことが可能です。
自己破産の手続中の転居については、以下の記事も参考になります。
(5)手続中に就くことができない職業・資格がある
管財事件となった場合には、手続中に一時的に就くことができなくなる職業や資格があります。
具体的には、以下のとおりです。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 保険募集人(保険外交員)
- 証券外務員
- 警備員 など
これらの仕事に就いている場合、免責許可決定を受けるまでの間は業務を行うことができず、休職や転職をしなければならないケースがあります。
なお、免責許可決定を受けた後は、従来どおり仕事をすることができます。
手続中の資格や職業の制限については、以下の記事でも詳しく解説しています。
(6)手続中は郵送物が破産管財人に転送される
手続中は、債務者宛の郵送物は破産管財人に転送されてしまうことに注意が必要です。
これは、破産管財人が債務者の財産を把握するために郵送物などの内容を確認する必要があるからです。
なお、破産管財人が内容を確認し、問題がないと判断した場合には債務者本人の手元に渡ります。
また、免責許可決定を受けることができれば、このような取り扱いも終了します。
まとめ
本記事では、自己破産の管財事件についてその流れや目安となる期間などについて解説しました。
管財事件として処理がなされると、債務者の財産を換価処分し、債権者に配当することが予定されるため、手続全体に要する期間が長期化する傾向があります。
また、裁判所によって破産管財人が選任されることで、手続中には様々な注意点があります。
これらを把握した上で手続を進めなければ、免責許可決定を受けられなくなる場合もあるため、注意が必要です。
そのようなリスクを抑え、見通しをもって手続を進めていくためにも、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの自己破産の手続に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、自己破産を行うことにお悩みの方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事