債権管理で知っておくべきポイントとは?債権の種類や消滅時効について

「何年も払ってもらえていない代金がある」
「売掛金の時効がいつかを把握していない」
「時効になりそうな未収金が複数ある」
未収金の管理や回収でお悩みの会社は少なくありません。
売掛金、代金、手数料、これらはすべて債権といいます。
債権には消滅時効があり、消滅時効が完成してしまうと請求する権利が失われてしまいます。
この記事では、債権管理で知っておくべきポイント、消滅時効とはどのようなものか、そして、時効の完成を防ぐ方法について解説します。
1.債権には消滅時効があるのか

消滅時効とは一定期間、債権を行使しないと債権が消滅することをいいます。
売掛金や貸付金があっても、一定期間何もしないで放置していると相手方に請求することができなくなってしまいます。
一度時効が成立した場合、債権者の側の救済措置は基本的にありません。
2.債権の種類について
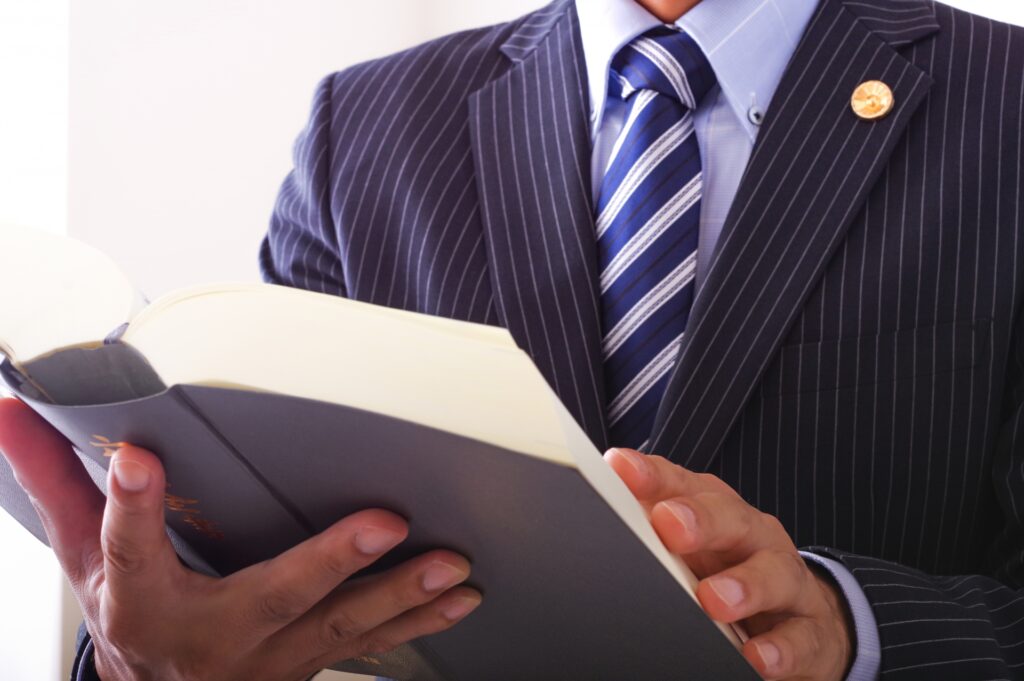
債権の種類には下記の表のようにいろいろなものがあります。
| 債権の種類 | 具体例 |
| 運送費 飲食・宿泊代金の債権 短期間の動産の賃貸料の債権 |
宅配便の運賃 飲食店、ホテルなどの料金 レンタルDVD、レンタカーの料金 |
| 教育に関する債権 商品の売買代金の債権 給料債権 弁護士、公証人の報酬の債権 |
学校や塾の授業料 商品の売掛金 給与・賞与 弁護士・公証人の報酬 |
| 医師・薬剤師の報酬の債権 工事代金の債権 不法行為に基づく損害賠償請求権 |
医師・薬剤師の報酬の債権 建築工事の代金 交通事故の慰謝料等 |
| 定期給付債権 | 金銭の貸付 家賃 |
| 小切手債権、約束手形債権 | 小切手所持人の小切手上の債務者に対する請求権 約束手形を受け戻した裏書人の他の裏書人に対する請求権 約束手形所持人の裏書人に対する請求権 約束手形の振出人に対する請求権 |
3.債権の消滅時効の期間

債権の消滅時効が完成するまでの期間は、民法166条1項により、次のように定められています。
| 民法166条1項
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 |
(1)「権利を行使することができる時」とは
権利を行使することができる時というのは、契約時に支払期日を定めていれば、その支払期日の翌日です。
支払う金額だけを決めていた場合など、支払期日を定めていない場合はいつでも支払いを請求することができますので、契約の翌日が権利を行使することができる時となります。
(2)債権の消滅時効の期間はほとんどの場合は5年
条文には、「権利を行使することができることを知った時」とあります。
契約に定めている場合、当事者は当然支払期日を定めたことを知っていますから、その日以降に権利を行使できることを知っていることになります。
したがって、ほとんどの場合、消滅時効が完成するのは支払期日の翌日から5年ということになります。
(3)改正前の民法が適用される場合がある
時効について定める民法は、数年前に大規模な改正が行われ、令和2年4月1日に施行されたものです。
この改正には改正附則によって、改正前の規定からの経過措置が定められています。
そして、消滅時効については、施行日前に生じた債権については改正前の規定が適用される、とされているのです。
改正前の規定においては、権利を行使できる時から10年が債権の消滅時効の期間でした。
しかし、このほかに商行為によって生じた債権について5年の商事消滅時効が定められており、さらに、以下のような債権については短期の消滅時効が定められていました。
| 債権の種類 | 消滅時効の期間 |
| 運送費 飲食・宿泊代金の債権 短期間の動産の賃貸料の債権 |
1年 |
| 教育に関する債権 商品の売買代金の債権 給料債権 弁護士、公証人の報酬の債権 |
2年 |
| 医師・薬剤師の報酬の債権 工事代金の債権 不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
| 定期給付債権 | 5年 |
これらの債権が令和2年3月31日以前に生じている場合は、改正前の規定が適用されるため、注意が必要です。
(4)手形債権、小切手債権の消滅時効は民法と別に規定されている
手形債権、小切手債権については、手形法、小切手法が個別に消滅時効を定めているため、上記の民法の規定の適用がありません。
そのため、改正の前後に関わらず、独自の消滅時効期間が適用されます。
約束手形、小切手に関する債権の消滅時効期間は以下のとおりです。
| 債権の種類 | 消滅時効の期間 |
| 小切手所持人の小切手上の債務者に対する請求権
小切手を受け戻した小切手上の債務者の他の債務者に対する請求権 約束手形を受け戻した裏書人の他の裏書人に対する請求権 |
6か月 |
| 約束手形所持人の裏書人に対する請求権 | 1年 |
| 約束手形所持人の振出人に対する請求権 | 3年 |
約束手形、小切手に関する債権については、民法とは別にこれらの時効期間が定められていますのでこれも注意が必要です。
4.消滅時効の完成を回避する方法

債権を消滅時効にかからせることなく回収するためには、以下の方法が考えられます。
- 時効の成立前に回収する
- 時効の完成をストップさせる
- 時効を更新する
順にご紹介します。
(1)時効の成立前に回収する
時効が成立する前に債権が回収できるように債権管理をしていれば、消滅時効による不利益を受けることもありません。
(2)時効の完成をストップさせる
時効は、一定の事由の発生によってその進行を止めることができます。
これを「時効の完成猶予」といいます。
時効の完成猶予となる事由には、下記のようなものがあります。
- 催告
- 裁判上の請求
- 強制執行、仮差押え等
#1:催告
催告とは裁判を使わない請求のことです。
債権者に対し、債務の履行を請求する内容証明郵便等を送付することにより、消滅時効の進行を中断させることができます。
ただし、催告によって猶予が与えられるのは6か月間であり、その6か月が経過すれば時効は完成してしまいます。
催告は、あくまで一時的な猶予を得るための手段ですので、6か月の間に、次の裁判上の請求などを行う必要があります。
また、催告の方法は、法律上指定されているわけではありません。
そのため、口頭で行うことでもかまわないということです。
しかし、のちの裁判の際に催告した事実の有無を争われた場合、催告を口頭で行っていたときは証拠がありません。
内容証明郵便であれば、相手に催告が送付されたことや催告の内容を証拠として残すことができます。
催告を行う際には内容証明郵便の利用をお勧めします。
催告による時効完成の猶予がされている場合、その期間中に再度の催告をしてもその催告にはもう時効完成の猶予の効力はありません。
なお、催告による時効完成の猶予が与えられるのは、1回だけということになります。
#2:裁判上の請求
裁判上の請求とは、言葉のとおり、裁判所への訴訟提起による請求や、支払督促の申立てなどを指します。
#3:強制執行、仮差押え等
これらはいずれも裁判所が関与する手続のため、あまり馴染みがないかと思われます。
強制執行は、債権者が債務者に対して持っている権利(債権)を国家権力によって強制的に実現する手続です。
判決が出ても支払ってこない債務者に対する次の手段といえます。
仮差押えは、裁判手続中に裁判の目的である財産が失われないために、裁判所が債務者の財産処分行為に一定の制約を課す手続です。
(3)時効を更新する
時効は、一定の事由の発生によりリセットすることができます。
これを「時効の更新」といいます。
時効の更新事由があった場合、その時点から再度時効の期間が開始することになります。
時効の更新となる事由には、下記のようなものがあります。
- 判決の取得
- 債務の承認
#1:判決の取得
裁判上の請求により時効の完成猶予を得て、さらに判決を取得することができた場合には、その確定の時から新たに消滅時効が進行することになります。
#2:債務の承認
債務の承認とは、債務者が債務を負っていることを認めることです。
たとえば、債権回収のために債務者に支払いを求めた際に、「来月まとめて支払うので待ってほしい」と言われた、全額を直ちに支払うことができないものの、半分の支払いをひとまず受けたといったことが考えられます。
そのほか、債務者が債権の一部でも支払いを行えば、それも承認にあたります。
したがって、数千円でも債務者に支払ってもらえれば、時効の更新の効果が得られます。
いずれの方法をとるにしても、裁判所の手続を経ないので、簡単に低費用で行うことができます。
債務の承認は、債務者が口頭でしただけでも成立します。
しかし、債権回収が難航して裁判になった場合には、債務の承認があったことを債権者が証明しなければなりません。
証拠としては、主に①書面、②メール、③録音が効果的です。
①書面は、支払いを猶予したり、まずは一部だけでも支払いを受けたりする場合に、債務者の代表者から「貴社に対し●●円の債務があるが、●年●月●日までに支払います」といったものを一筆とっておけば十分で、正式な書面である必要はありません。
②メールは、債務者が書面作成に渋ったり、警戒したりしている場合に有効です。
日時、送信者も記録されるので裁判での信用性も高いです。
③録音は、債務者と電話や直接話す場合に録音をICレコーダー等で行います。
最近はスマートフォンに録音機能が付いていることも多いので利用しやすくなっています。
録音していることを債務者に知らせなくても直ちに証拠として使えなくなるということはありません。
5.消滅時効の期間を過ぎてしまった場合の対処法

実は、消滅時効の効果は、時効の完成だけでは発生しません。
債務者が「時効の援用」をして初めて効果が生じます。
時効の援用とは、債務者が時効の効果を主張することです。
時効が成立した場合、債権者の側の救済措置は基本的にありません。
債務者側に働きかけて、何らかの行動をとらせることが必要です。
(1)時効援用をさせない
債権者が消滅時効による不利益を受けない方法として考えられるのは、債務者が時効を援用しないということです。
時効の援用をしないよう交渉するには、債務者にも何らかのメリットが必要です。
たとえば、債務者と今後も取引を継続する可能性がある場合には、今後の取引をある程度継続するということと併せて時効の援用をしないということを合意するなどして、時効の援用をしないよう交渉することができます。
(2)債務を承認させる
時効完成後であっても、債務の承認の効果は生じます。
そのため、消滅時効完成後に債務者に対して請求し、それに債務者が応じて一部でも支払いをすれば、その時点から新たな消滅時効期間を進行させることができます。
ただし、債務者が時効の完成に気付いていると、消滅時効を援用されてしまう可能性もあります。
そのような可能性がある場合には(1)の手段をとることになるでしょう、
まとめ
債権の消滅時効は、債権者にとっては大きな問題です。
しかし、時効成立させないためのスキームを十分に組んでおけば十分に避けられるリスクです。
ただし、そのようなスキームを自社で作成、維持していくことは負担が大きいので、債権の回収や管理については弁護士に継続して法的なアドバイスを受けることや依頼をすることが望ましいでしょう。
お気軽にご相談ください。
関連記事






