銀行の融資が返済できないときはどうするべき?その対処法を解説します

「銀行から受けている融資の返済の目途が立たない」
「銀行からの融資を返済できなければどのようなリスクがあるのか知りたい」
会社、法人の経営者の中には、このような悩みや疑問をお持ちの方もいると思います。
銀行から受けた融資については、あらかじめ定められた期日までに元本と利息を合わせた金額を返済しなければなりません。
しかし、キャッシュフローの不足や突発的な支出の増加などによって、銀行から受けた融資を期日までに返済できない事態が発生することもあります。
銀行から受けた融資が返済できないことは、企業の今後の経営に大きな影響を及ぼし、事業継続が困難となってしまう事態にもつながりかねません。
本記事では、融資を返済できない場合のリスクや避けるべき行動などについて解説します。
1.銀行の融資が返済できない場合に起こりうる影響

融資を返済できない状態が続けば、様々な問題が起こる可能性があります。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 貸主の金融機関から返済の督促や催促を受ける
- 遅延損害金が発生する
- 企業の信用力が低下する
- 法的措置に移行する可能性がある
今後の経営に大きな影響を与えるため、できる限り早期に返済することが重要です。
(1)貸主の金融機関から督促や催促を受ける
借入金の返済が滞ってしまうと、取引先である金融機関から督促や催促を受けます。
督促や催促には法的拘束力はないものの、無視し続けることによって訴訟などの法的措置に移行したり、分割支払いの期限の利益を喪失したりするリスクが高まります。
期限の利益とは、双方の合意により定められた返済期限までは全額返済しなくてもよいとする権利のことです。
しかし、期日までに返済することができず、督促等にも対応しないままでいると、分割払いになっている借入金について期限の利益を失い、債権者から残っている債務を一括で返済するように要求されたり、債権者である金融機関が財産等を差し押さえようと訴訟を起こしたりする可能性が生じます。
このように、金融機関からの督促には、次のステップに移行することを告知する側面もあるため、無視し続けることによって様々なリスクを抱えることになるのです。
(2)遅延損害金が発生する
当初の返済期日を経過しても返済ができない場合、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、返済を徒過したことに対するペナルティの意味も持つため、通常の金利よりも高い利率が設定されていることが一般的です。
遅延損害金には、法律によって定められた法定利率と、当事者間で定める約定利率があります。
特に、約定利率が法定利率(年3%)を超えるときは約定利率が優先されるため、返済しなければいけない金額が増えてしまうことに注意が必要です。
(3)企業の信用力が低下する
支払期限を1か月ほど経過すると、信用情報機関にその事実が登録されます。
登録されれば、今後他の金融機関から融資を受けたり取引先とやり取りする際に、信用情報機関への照会を通じて企業の支払能力に問題があることが知られ、融資や取引が不利となる可能性が高まるのです。
また、支払いが数か月にわたって行われない場合には、債権者である銀行から一括返済を求められるなどして、さらに資金繰りが悪化するリスクが高まります。
(4)法的措置に移行する可能性がある
長期間にわたって返済されない場合には、債権者である銀行は法的措置への移行を検討します。
具体的には、借入をする企業が融資を受ける際に担保として提供した不動産や設備などについて担保権を実行して競売手続に移行することがあります。
担保権の実行による競売手続では、市場価格よりも低い金額で財産が処分されるケースが多く、売却額が融資の残額を下回った場合には、債務者である企業はその差額の返済義務を負うことになります。
特に事業に必要な財産が競売にかけられてしまうと、事業継続が困難になるケースもあるため、このような事態に陥る前に対応を行うことが必要不可欠です。
2.銀行の融資を返済できない場合に避けるべき行動

銀行から受けた融資の返済ができない場合には、資金調達を行って返済することも1つの解決方法です。
しかし、以下のような資金調達の方法は、企業の資産状況がさらに悪化することにつながるため、避けなければなりません。
- 返済のために安易にほかの金融機関から借入れを行う
- ファクタリングなどによって資金調達を行う
順にご説明します。
(1)返済のために安易にほかの金融機関から借入れを行う
銀行融資の返済に安易にほかの金融機関から借りた資金を充てることや、返済のためにほかの金融機関から新たな借入れを行うことは避けましょう。
将来的に返済を行える見通しがない状態でこれらの対応を行っても、借金が増える一方であり、根本的な解決にははらない上に、多重債務に陥ってしまいます。
また、複数の返済期日が同時に到来することになるため、手元に資金がないような場合には、返済のめどが立たないことから精神的負担を増やすことにもつながります。
(2)ファクタリングなどによって資金調達を行う
ファクタリングとは、企業が有する債権について、履行期が到来する前に第三者に譲渡して現金化する資金調達の方法です。
主に売掛金債権や請負代金債権などがファクタリングとして利用されており、これらの債権の支払期日前に現金を手にすることができます。
もっとも、ファクタリングを利用する際には、債権額の全額を受け取れるわけではなく、高額な手数料が差し引かれた金額を受け取ることになります。
つまり、法人が持っている売掛金等の債権が目減りしてしまうのです。
そのため、ファクタリングを利用して資金調達を行ったとしても、支出が増加し資金繰りを解決する方法にはならないことに注意が必要です。
ファクタリングの概要や企業の資金繰りに与える影響などについては、以下の記事も参考になります。
3.返済できない場合の対処法
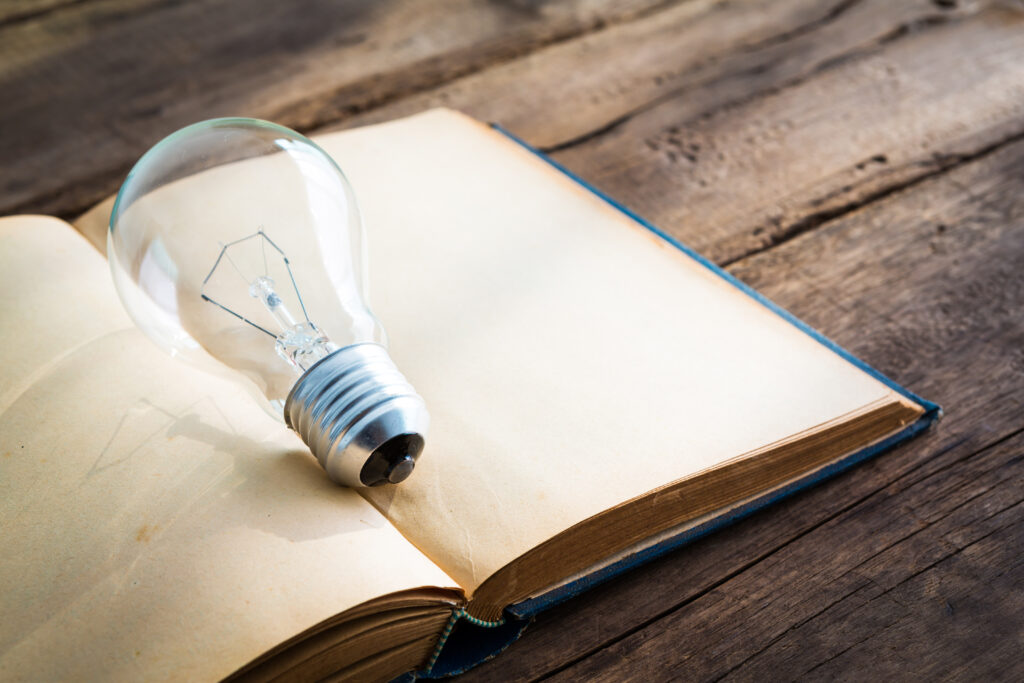
銀行融資が返済できない場合には、まずは債権者である銀行に相談することが重要です。
相談することで、以下のような対処について銀行側と合意できる可能性があります。
- 追加融資を受ける
- 返済期日のリスケジュールを行う
順に見ていきましょう。
(1)追加融資を受ける
追加融資とは、債権者である銀行からすでに融資を受けている状態のまま、改めて2回目以降の借入れを行うことです。
返済中に同じ債権者から借入れを行うことになるものの、他の金融機関から新たに融資を受けるよりも柔軟に対応してもらえることもあります。
もっとも、返済がすでに遅れている場合には企業の信用力も低下しているため、初回の融資より審査が厳しくなり、追加融資を受けられないことがあることにも注意が必要です。
万が一資金繰りが悪化し返済が苦しい場合には、返済が遅れてしまう前に早期に銀行へ相談することが重要です。
(2)返済期日のリスケジュールを行う
リスケジュールとは、返済期日や返済金額などの借入条件を変更することです。
返済期限の延長や毎月の返済額の減額など、返済計画などの見直しを交渉できるため、資金繰りの改善を図ることができます。
リスケジュールの相談を受けた銀行は、企業の事業継続の見通しや返済意思などを慎重に評価した上で応じるか否かを決定します。
そのため、現在の収支状況や改善策などを提示することで、リスケジュールに応じてもらえる可能性が高まります。
もっとも、返済期間を延長すればその分利息の支払いは増えますので、リスケジュール後の資金繰りが悪化しないように事業収益の見通しを慎重に立てることが重要です。
収支の見直しなどの改善策を講じても資金繰りが好転せず、今後の返済が難しい場合には、弁護士に相談の上で、法人破産を行うことを検討することも視野に入れましょう。
4.弁護士に法人破産について相談するメリット

法人破産とは、債務の返済ができなくなった会社、法人を清算する法的手続です。
法人破産を行うことで、会社、法人の法人格が消滅するとともに、債務についても消滅します。
メリット・デメリットを理解したうえで慎重に判断することが重要であるため、弁護士に相談のうえ手続を進めるようにしましょう。
弁護士に法人破産について相談するメリットは、以下のとおりです。
- 法人破産を行う際のアドバイスを受けることができる
- 書類作成や裁判所、管財人との対応を任せることができる
- 費用負担を低く抑えて手続を行える可能性がある
法人破産の手続の流れや弁護士に申立てを依頼した方が望ましい理由などについては、以下の記事でも解説しています。
(1)法人破産を行う際のアドバイスを受けることができる
法人破産は、裁判所を通じて行うため、法律で定められた要件を満たす場合しか手続を行うことができません。
そこで、弁護士に相談することで、法人破産を行う要件を満たしているか、また、手続を行うことによる影響なども事前に説明を受けることができます。
あらかじめ注意点などを押さえた上で検討できるため、破産に向けた適切な対応を取りやすくなります。
なお、法人破産を申し立てるための要件について、詳細を知りたい方は以下の記事もご参照ください。
また、法人破産を申し立てることができる申立権者や手続を行う際の注意点などについては以下の記事においても解説しています。
(2)書類作成や裁判所、管財人との対応を任せることができる
法人破産を行う際には申立書類の作成のほか、添付資料の収集などを行い、裁判所に提出する必要があります。
手続を正確に進めるためには実務経験や専門知識が求められますので、自力で進めることが難しいことが通常です。
スムーズに進めるためには、専門家のサポートを必要とすることが多数あるため、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すると手続を一任でき、書類作成や資料収集を任せたりアドバイスやサポートを受けたりできるため、複雑な法人破産の手続も終了までの見通しをもって進めることができます。
法人破産を申し立てる際に必要となる書類や資料については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(3)費用負担を低く抑えて手続を行える可能性がある
法人破産手続を行うためには、裁判所に予納金を支払わなければなりません。
予納金の金額は債務総額、債権者数、事業所の数、従業員数などの状況によって定められるため、債務総額や債権者の数が少なければ予納金の額もそれに伴い低額になります。
ただし、予納金の金額を低くするためには、弁護士に破産申立について依頼していることが条件になることがあります。
破産申立を弁護士に依頼すれば、その弁護士によって事案の整理が図られ、裁判所や破産管財人の負担軽減が図られることが主な理由です。
そのため、弁護士に相談・依頼することで、予納金の金額を低く抑えて手続を進めることができることがあるのです。
ただし、予納金を捻出できないほど資金繰りが悪化している場合には、法人破産を行うこと自体が困難となります。
選択肢が限定されないためにも、資金繰りの悪化や返済の目途が立たなくなった時点で、なるべく早期に弁護士に相談しておくことも大切です。
法人破産を行う際に必要となる予納金の項目や相場については、以下の記事もご覧ください。
また、法人破産の手続を行うことを検討すべきタイミングについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
まとめ
銀行の融資が返済できない場合には、企業の信用力の低下によって事業継続が困難になるなど、様々な影響が生じる可能性があります。
また、銀行融資を返済するための資金が不足している場合でも、安易にほかの金融機関から借入れを行ったり、売掛金債権などをファクタリングを利用して現金化したりすることは避けなければなりません。
資金繰りが悪化し、法人の資金が枯渇してしまう前に、法人破産を行うことも視野に入れながら、弁護士に相談してみることが重要です。
弁護士法人みずきでは、法人破産の問題に慣れた弁護士が多数在籍しておりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
関連記事
























