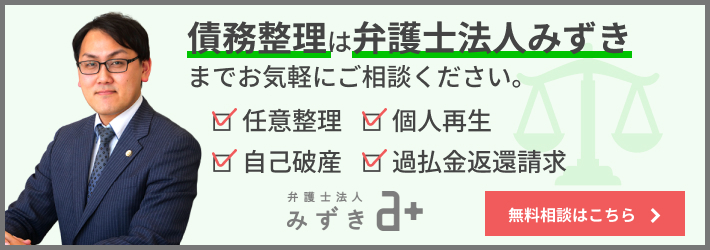個人再生とは?弁護士が手続の概要やメリット・デメリットなどを解説

「個人再生って具体的にどんなことをするのか」
「個人再生をすることでどのような影響が生じるのか」
借金の返済で困っている方の中には、債務整理を行うことを検討されている方もいると思います。
債務整理には任意整理手続、個人再生手続、自己破産手続の3つがありますが、そのうちの個人再生手続について、このような疑問や不安をお持ちの方もいるでしょう。
本記事では、個人再生の概要やメリット・デメリットなどについて解説します。
これから個人再生を行うことを検討されている方の参考となれば幸いです。
1.個人再生手続の概要

個人再生手続は、借金の救済制度である債務整理の方法の1つです。
同じ債務整理の手続である任意整理手続とは異なり、裁判所を介して行う点に特徴があります。
以下では、個人再生手続の概要や手続の種類などについて解説します。
(1)個人再生手続とは
個人再生手続とは、裁判所に申立てをして借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、借金をその金額に応じた割合で減額し、原則3年間で返済する再生計画案について裁判所の許可を受けたら、その計画どおりに返済していく手続です。
任意整理よりも大きく債務額を減らすことができる手続であり、一般的にはギャンブル等の浪費で借金を作ってしまい破産が難しい場合や、住宅ローンの残った自宅を手元に残したい場合に検討することが多い傾向があります。
なお、個人再生手続を行うことが適している人の特徴については、以下の記事もご参照ください。
(2)個人再生手続の種類
個人再生手続には主に2つの手続があります。
- 小規模個人再生手続
- 給与所得者等再生手続
このうち、ほとんどのケースでは、小規模個人再生手続で行われています。
小規模個人再生手続は、特定の条件(将来の継続的な収入が見込まれること(給与所得者も含む)、住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円を超えないこと等)を満たしていれば誰でも利用できるのに対し、給与所得者等再生手続は、会社員や公務員のように安定した収入が見込める給与所得者(過去2年間の収入の変動幅が20%未満であること)に限定されている点が特徴です。
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の概要や違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
2.個人再生の要件

個人再生手続は、借金返済に困っている人であれば誰でも利用できる手続ではなく、特定の要件を満たして初めて借金の減額を受けることができます。
主な要件は、以下の2つです。
- 開始要件
- 認可決定要件
順にご説明します。
なお、個人再生を行うための要件については、以下の記事も参考になります。
(1)開始要件
個人再生手続は、裁判所に申し立てることによって、手続が開始します。
個人再生手続の開始の主な要件としては、以下のものがあります。
- 債務者に破産手続開始の原因となる事実(支払不能)の生ずるおそれがあること
- 債務総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満であること
- 定期的な収入を得る見込みがあること
個人再生手続を行う場合、住宅ローンを除いた5000万円未満の債務について、これを弁済する資金が継続的に不足していることから、契約内容にしたがって返済を行うことが困難(支払不能)と認められなければなりません。
また、個人再生手続は認可決定後、3年にわたって計画案通りの返済を継続しなければならないため、継続的に安定した収入を得る見込みがあることが前提となります。
なお、給与所得者等再生手続を行う場合には、上記に加えて、「過去7年以内に自己破産や給与所得者等再生手続を行っていないこと」も必要です。
(2)認可決定要件
個人再生手続を申し立てた後は、裁判所から指定された期日までに再生計画案を作成し、提出する必要があります。
再生計画案の内容について、裁判所の認可を受けて返済計画が開始されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 再生計画案を期日までに提出していること
- 再生計画の内容が適切に定められていること
- 再生計画が実行できる見込みがあること
なお、小規模個人再生手続の場合には、再生計画案に対して債権者の過半数の同意を得なければ認可を受けることができない点に注意しましょう。
具体的には、債権者の過半数が反対(不同意)している場合と借金総額の過半数の金額の債権を有する債権者が反対(不同意)している場合は、認可を受けることはできません。
給与所得者再生の場合は、債権者の過半数の同意は必要ありません。
3.個人再生手続のメリット

個人再生手続を行うことでさまざまなメリットがあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 借金の減額を受けられる
- 借金の理由は問われない
- 資産価値の高い財産を引き続き手元に残すことができる
- ローンが残っている住宅を手元に残せる可能性がある
順にご説明します。
なお、以下の記事でも解説しているので、合わせてご参照ください。
(1)借金の減額を受けられる
個人再生手続は元金も含めて減額してもらえるので、借金の返済負担の軽減が期待できます。
再生計画案は、個人再生手続で定められている最低弁済額基準または清算価値保障原則に基づいた基準のいずれかで算定し、返済計画を立てることになります。
最低弁済額基準に該当する場合、債務総額に応じて、以下のように定められています。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万円超え3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円超え5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
借金総額によっては、最大10分の1まで減額されるので、着実に返済負担を軽減することができます。
なお、個人再生における減額幅のルールについては、以下の記事でも解説していますので、ぜひご参照ください。
(2)借金の理由は問われない
個人再生手続の場合、借金の理由は問われないため、ギャンブルや浪費が原因の借金でも減額を受けることが可能です。
他方で自己破産手続では、借金の主な原因がギャンブルや浪費であった場合、借金の返済義務が免除されない「免責不許可事由」に該当し、借金をゼロにできない可能性があります。
個人再生手続では、この免責不許可事由について考える必要がないため、これらの事情によって借金をした場合であっても、安心して手続きを進めることが可能です。
(3)資産価値の高い財産を引き続き手元に残すことができる
資産価値の高い財産を引き続き手元に残すことができる点も個人再生手続の特徴です。
自己破産手続の場合、住宅や車・バイクなど一定の資産価値がある財産をお金に換えた上で、債権者に配当することになります。
つまり、自己破産手続を行うと一定以上の価値がある財産を手元に残すことができません。
しかし、個人再生手続では、財産の換価処分が行われるわけではないため、高額な財産を手元に残しながら手続を行うことができます。
もっとも、車やバイクに関しては、ローンを完済している場合には手元に残すことができるものの、残債がある場合には信販会社に引き上げられてしまう可能性が高い点には注意しましょう。
車やバイクのローンには、信販会社がローンの残債を回収できない場合に備えて所有権留保を付していることが多いからです。
個人再生手続を行ったことは、ローンの残債を支払うことができないことを意味するため、信販会社に車やバイクを引き上げられてしまいます。
(4)ローンが残っている住宅を手元に残せる可能性がある
個人再生では、ローンが残っている住宅を手元に残せる可能性があります。
具体的には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンの残債がある住宅については引き続き手元に残しながら手続を行える可能性があります。
住宅資金特別条項を利用するための要件は、以下のとおりです。
- 住宅ローンの借入れであること
- 債務者が居住用に所有する住宅であること
- 住宅をほかの借入れの担保としていないこと
- 保証会社が代位弁済した場合には、その履行日から6か月以内に再生手続の申立てを行っていること
住宅資金特別条項を利用した場合、住宅ローンの返済についてはこれまでの契約内容に従って継続する必要があります。
また、住宅資金特別条項を利用するためには早期の準備や対応を行うことが必要となるため、速やかに弁護士に相談しましょう。
4.個人再生手続のデメリット

個人再生手続には、大幅な借金の減額を受けられるメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。
たとえば、以下のとおりです。
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 官報に氏名や住所が掲載される
- 手続を行うのに時間がかかる
順に見ていきましょう。
なお、以下の記事でも個人再生のデメリットについて解説しているので、合わせてご覧ください。
(1)信用情報機関に事故情報が登録される
個人再生手続に限らず、債務整理全般に言えることですが、手続を行うと信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されてしまいます。
信用情報機関とは、加盟している金融機関から顧客の借入れ経過や返済状況などの信用情報の提供を受けて、これを管理している機関です。
事故情報が登録されているということは、その人の返済能力に問題があることを意味するため、クレジットカードの利用や新たな借入れができなくなってしまいます。
なお、事故情報の登録期間は個人再生手続の場合、手続の開始決定から10年とされているため、その間はクレジットカードやローンの利用ができないことに注意が必要です。
(2)官報に氏名や住所が掲載される
個人再生手続を行うことで、官報に氏名や住所が掲載されてしまいます。
官報とは、政府の機関誌であり、国家の決定事項や国民の権利義務に関連する各種の公告が掲載されている媒体です。
もっとも、日常的に目を通している人は限られているため、官報に個人情報が掲載されたからといってすぐに周囲に知られる可能性は低いと言えます。
ただし、何らかのきっかけで周りの人に知られてしまう可能性がある点には注意が必要です。
(3)手続を行うのに時間がかかる
手続を行うのに時間がかかる点もデメリットと言えるでしょう。
個人再生手続は裁判所を介して行う手続であり、申立要件や財産の調査、再生計画案の審査などが厳格に行われ、申立てから決定まで4~6か月程度かかるのが一般的です。
なお、手続に要する大まかな時間や手続の流れについては、以下の記事もご参照ください。
5.個人再生手続の流れ

個人再生手続の流れは、以下のとおりです。
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知の送付・財産調査
- 個人再生手続の申立て
- 再生手続開始決定
- 履行テスト
- 再生計画案の作成・提出
- 再生計画案の認可決定・返済の開始
なお、手続の流れや詳細については、以下の記事も参考になります。
(1)弁護士に相談・依頼
個人再生手続を検討している方は、まずは早い段階で弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、手続の流れや見通しなどについて具体的に説明を受けることができます。
また、借入総額や収入状況などを踏まえて、個人再生を行うことができるかどうかについてもアドバイスを受けることが可能です。
個人再生手続は裁判所を介して行う手続であり、申立書面や再生計画案の作成など、様々な書類作成・資料収集が必要となります。
弁護士に相談の上、手続を依頼すれば、書類作成や資料収集についてもアドバイスやサポートを受けることができ、スムーズに手続を進めることが可能です。
(2)受任通知の送付・財産調査
弁護士が受任をした後に、債権者に対して受任通知が送付されます。
債権者は受任通知を受け取った後、債務者に対して直接督促や取立てを行うことができなくなるため、弁護士との契約後はしばらくの間返済が停止します。
受任通知の送付のタイミングで、並行して債務者の財産調査が行われます。
また、申立てに向けた準備についても、弁護士からアドバイスやサポートを受けながら進めていきましょう。
(3)個人再生手続の申立て
必要書類や資料が揃ったら、裁判所に対して書類等を提出して個人再生手続の申立てを行います。
申立ての際には、申立書以外にも債権者一覧や財産目録、家計収支表などの提出をする必要があります。
漏れがないように弁護士と協力しながら申立ての手続を進めましょう。
なお、個人再生手続を行うにあたって必要となる書類については、以下の記事でも詳しく解説しています。
(4)再生手続開始決定
個人再生手続の申立て後は、申立書類の審査を経て、再生手続を開始する要件を満たしていると裁判所が判断すると、再生手続開始決定が下されます。
再生手続開始決定は、概ね申立てから1か月以内になされることが多いです。
裁判所の運用によっては、個人再生委員が選任されることもあり、選任された場合には個人再生委員との面談が行われ、個人再生に至った経緯や財産状況などについて正確に伝えることが求められます。
(5)履行テスト
申立てがなされた後、約6か月にわたって履行テストが行われます。
履行テストとは、裁判所として、申立人が認可された再生計画案に従って継続的に返済を行っていくことができるかどうかを確認するために行うものです。
これは、再生計画案で予定されている金額を毎月指定された口座に振り込むことによって実施されます。
なお、履行テストの支払いを1回でも怠ってしまうと、手続が中止(廃止)となってしまう可能性があるため、支払いを怠ることなく対応することが重要です。
(6)再生計画案の作成・提出
減額された借金をどのように返済していくかについて記載した書類(再生計画案)を裁判所に提出し、裁判所に認可してもらうことで借金の減額が認められます。
再生計画案は、裁判所が指定する期日までに作成して提出しなければなりません。
1日でも期限を徒過した場合には認可決定が下されないため、期日を守って作成・提出する必要があります。
(7)再生計画案の認可決定・返済の開始
再生計画案が認可された後は、再生計画の内容に従って返済を開始します。
原則3年にわたって返済を行うものの、事情によっては5年の返済期間が認められるケースもあります。
もっとも、収入や支出の状況から、3年では返済が困難であるような「特別の事情」が認められなければならず、5年の返済スケジュールが認められることはそれほど多くありません。
5年の返済期間が認められるような「特別の事情」の具体例については、以下の記事も参考になります。
6.個人再生の注意点

個人再生を行う際には、いくつかの注意があります。
主な注意点は以下のとおりです。
- 特定の債権者のみに優先的に返済をしない
- 最低弁済額まで減額されるとは限らない
順にご紹介します。
(1)特定の債権者のみに優先的に返済をしない
個人再生手続を開始する場合には、特定の債権者のみに優先的に返済しないことが大切です。
裁判所を介して行われる個人再生は、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」という考え方に基づいて進められます。
そのため、特定の債権者のみに優先的に返済を行う行為は「偏頗弁済」とされ、禁止されているのです。
偏頗弁済をしたことが裁判所等に知られると、個人再生手続の申立てが不正・不誠実な目的のもとでなされたと裁判所に判断され、手続の継続が困難となってしまう可能性があります。
手続を安定的に進めるためにも、手続を行う際には特定の債権者を優遇する行為を行わないようにしましょう。
なお、個人再生手続と偏頗弁済の関係については、以下の記事も参考になります。
(2)最低弁済額まで減額されるとは限らない
個人再生手続では、自己名義の財産を全て処分した場合にのみ借金をゼロにする自己破産手続とは異なり、債務者の財産は処分されずに借金の大幅な減額がなされます。
個人再生手続を選択した場合に、自己名義の財産を換価した場合の総額を下回る金額の返済しかしないでよいということになれば、破産手続と個人再生手続との公平が保てなくなります。
そこで、個人再生手続における清算価値保障原則は、債務者が債権者に返済すべき最低限度の基準を定めています。
このような考え方を採用することで、債務者と債権者の利益調整を図る機能を持っています。
そのため、清算価値の基準で算定される場合もあり、必ずしも最低弁済額まで減額されるとは限らないことには注意が必要です。
清算価値保障原則の概要や具体的な算定方法については、以下の記事で解説しています。
まとめ
個人再生手続は債務整理の手段の1つで、借金の大幅な減額を受けることができます。
また、信用情報機関に事故情報が登録されたり、官報に個人情報が掲載されたりといったデメリットがある一方で、最大10分の1まで借金を減額できる点が大きなメリットです。
利息のカットだけでは完済が難しい方は、個人再生手続を行うことを検討してみましょう。
もっとも、個人再生手続を行うためには一定の要件を満たす必要があります。
また、一定額以上の財産を所有している場合には、必ずしも最低弁済額まで減額を受けられない可能性があります。
そのため、個人再生手続を行うことを検討している方は、まずは弁護士に相談して、解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で受け付けておりますので、個人再生を行うことを検討している方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事